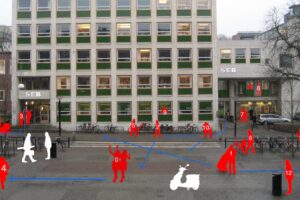母の聖戦(2021)
La Civil
監督:テオドラ・アナ・ミハイ
出演:アルセリア・ラミレス、アルバロ・ゲレロ、アジェレン・ムソetc
評価:70点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
第34回東京国際映画祭(2021)コンペティション部門にて上映された『市民』が邦題『母の聖戦』に改め、2023/1/20(金)より公開される。本作は、プロデューサーにカンヌ国際映画祭の常連閉塞感もの監督ダルデンヌ兄弟、クリスティアン・ムンジウ、ミシェル・フランコが肩を並べていることからも分かる通り相当な骨太作品だ。監督はルーマニア出身の女性監督テオドラ・アナ・ミハイ。チャウシェスク政権時代に亡命し、それ以降国外で映画製作をしている方である。今回が長編初監督、しかも舞台がメキシコという異例の作品となっている。その異例さにあぐらをかくことない映画に仕上がっていました。
『母の聖戦』あらすじ
組織犯罪に巻き込まれて行方不明になった娘の行方を捜すシエロは、凄惨な実態を目撃して…。ルーマニアの女性監督がダルデンヌ兄弟のプロデュースによりメキシコで撮影した作品。
※第34回東京国際映画祭より引用
誰も守ってくれない世界とは何か?
シエロ(アルセリア・ラミレス)は女手ひとつで娘ラウラ(デニッセ・アスピルクエタ)を育てている。そんな彼女が突如誘拐された。チンピラが現れ、15万ペソ(約37万円)と車を要求してくる。なんとか資金繰りを行い、チンピラに金と車を渡すが、彼女は帰ってこなかった。怒りと悲しみに暮れる彼女は警察に相談するも取り合ってくれない。やがて、若い女性が殺害されたニュースを目撃し、ラウラなのではと思い始める。
本作は、機能不全となった社会を描いている。警察も役所もシエロの話はとりあえず聞く。しかし、実効的な手段に出ることはない。システム化された仕事に従うが、情によってシステムのルールを変えることはない。だから、彼女がニュースを見て、遺体を確認したいと管理する者に懇願しても頑なに拒む。警察も、組織壊滅のために銃撃戦を始めるが、それはあくまで犯罪組織壊滅が目的であり、シエロの痛みに歩みよることはない。このような「誰も守ってくれない世界」において一般市民は孤独なわけだが、それは犯罪組織であっても同様だと映画は描く。チンピラは、都合が悪くなったら斬り捨てられるのである。
被害者/加害者の目線から斬り捨てられる社会像を描くことで、助けを求める市民に手を差し伸べる存在である警察がなぜ無力なのかが浮き彫りとなる。それは、「誰も守ってくれない世界」において重要なことは保身であり、与えられたシステム化された仕事をこなすことが自分の身を守ることなのである。それから逸脱した途端、冷たい社会に投げ出されてしまう。
実際にテオドラ・アナ・ミハイ監督は第34回東京国際映画祭での記事にて次のように述べている。
当時のルーマニアは市民同士が監視して告発しあう社会で、誰も信頼できませんでした。幼いながらも荒廃した社会を見てきたことが、私の人格形成に大きな影響を及ぼしています。『市民』の底流に流れている感情もまさしくそうで、頼る人間は誰もおらず、警察当局や男尊女卑の風習と闘い、乗り越えていくのは自分しかいないと、主人公のシエロは考えています。
ルーマニアでの肌感覚をメキシコに転用し、普遍的な物語へと昇華しているわけだが、これは今の日本も他人事ではないだろう。システムや強い者に従うことでしか自分を守れない冷たさ。そこから外れた人は、荒廃した地を這うことになる社会。心にずっしりくる作品であった。
日本公開は2023/1/20(金)。
第34回東京国際映画祭関連記事
・【東京国際映画祭】『スワン・ソング』ウド・キアの頭にシャンデリア
・【東京国際映画祭】『洞窟』タナトスとエロス
・『CRYPTOZOO』天才!キメラどうぶつ園
・【SKIPシティ国際Dシネマ映画祭】『夜を越える旅』モラトリアムが背中で語るまで
・【東京国際映画祭】『クレーン・ランタン』ヒラル・バイダロフ物語らない※ネタバレ
・【東京国際映画祭】『ザ・ドーター』言葉の呪いが不安定の渦に追い込む
・【東京国際映画祭】『ある詩人』広大な文学の地が失われる轍※ネタバレ
・【東京国際映画祭】『アリサカ』修羅場映画のスペシャリスト、ミカイル・レッド
・【東京国際映画祭】『カリフォルニエ』自分のモノがないこと、自分のジカンがないこと
・【東京国際映画祭】『ヴェラは海の夢を見る』身体と言葉を繋ぐ者ですら
・【東京国際映画祭】『牛』アンドレア・アーノルドの軟禁牛小屋※ネタバレ
・【東京国際映画祭】『リンボ』辺獄の果てまでどこまでも
※映画.comより画像引用