冬時間のパリ※旧題:ノン・フィクション(2018)
英題:Non-Fiction
原題:Doubles Vies
監督:オリヴィエ・アサイヤス
出演:ギヨーム・カネ、ジュリエット・ビノシュ、
ヴァンサン・マケーニュ、クリスタ・テレetc
評価:70点
東京国際映画祭が今年もやってきました。今年は東京フィルメックスに予算を回すため、そこまであまり本祭では映画を観ないのだが、オリヴィエ・アサイヤスの新作に惹かれてチケットを取ってみました。
そして、今回の『ノン・フィクション』は出版社の編集者が、デジタル書籍化にビジネスの舵を切るかどうかで悩む話だと聞いて、アサイヤスの集大成を期待した。そして、良い意味で裏切られた。Filmarksではネタバレなしで感想を書いたので、ここではネタバレありで本作の魅力を掘り下げていく。
『ノン・フィクション』あらすじ
編集者のアランは、低迷する本の売り上げに対し、電子書籍化で乗り切るかどうか悩んでいる。そんな編集者の下で、本を執筆しているレオノールは彼に1年以上取り組んできた内容の出版を行わないと告げられ、哀しんでいるが、妻はそんな自分を癒してはくれない。そんな彼らは、業界人との会食で、本の価値をディスカッションし、それぞれの終止符を探していく…アサイヤス流白熱教室
本作は、原題が“Doubles Vies(二重生活)”となっている通り、二つの軸が入り混じる話である。また英語タイトルが“Non-Fiction”と、フィクションを書く小説家のフィクションな話にも関わらず、それを否定していくタイトルがつけられていることに着目すると興味深く楽しめる作品となっている。
まず、この映画は「本の価値はどこで決まるのか?」というアサイヤス監督の問題提起が最初にある。そこに、ホン・サンス的《情けない男の足掻き》という物語的推進力が蒸されていく構成になっている。アサイヤス映画といえば、一見ドキュメンタリータッチに見えるが、映像が画になっていて美しいというスタイルを毎回とっているイメージが強いが、本作では、まるでやる気がないかのように全編撮影されている。ただただグダグダとフランス人的ソワレのインテリゲンチャぶった駄話を映しているだけなのだ。これはIndieTokyoの記事《アサイヤス最新作『ノン・フィクション』—私たちは変わりゆく世界にどう適応するか/しないのか》によると、エリック・ロメールの『木と市長と文化会館 あるいは七つの偶然』の影響によるものなんだそう。
ただ、エリック・ロメールの駄話感をただ援用するだけならそこまで面白い映画にはならなかっただろう。やはり、ロメールのあの会話の妙というのは彼にしか出せない技術であるので。そこで、アサイヤスは物語の推進力として、ホン・サンスの映画のような自虐のユーモアを取り込んだ。
冒頭、編集者のアランと執筆者のレオノールがカフェで会話する。「『沼地』読んだよ、良かったよ!」みたいなビジネストークが始まるのだが、どうも歯車が噛み合っていない。会話にぎこちなさがある。そして、レオノールは何か言いたげにそわそわしている。そして、別れ際にその正体が明らかになる。レオノールはアランに「あの件はどうなった?」と訊く。アランは、何それ?という顔をする。レオノールは「あの出版の件だよ」という。するとアランは、「あぁ、あれか、中止になったよ。なんだ知らなかったのかい?」という。
レオノールは悲しみのあまり、妻に慰めてもらおうとする。しかし、プライドがあるので、婉曲的にいう。それを悉く妻がスルーするもんだから、自己アピールを強くしていくと、妻が「あんた、ひょっとして慰めてほしいの?」「ばかね。さっさと書き直しなさい」と一喝されるのだ。
ここで、この映画の仕組みが分かってくる。人々は察してほしいと行動するのだが、相手はその通りに動いてくれない。寧ろ、相手が欲する要求が見え見えであえて避けたくなる。だが、当の本人は頭隠して尻隠さず、全くそのことに気づいていなくて醜悪なプライドが露見し、そこが滑稽で笑えてくるのだ。アサイヤス監督とコメディは程遠いイメージが強かったが、なんとも高度な笑いをここでやってのけていることがよく分かります。
さて、そんなユーモアの下で繰り広げられる議論のテーマが非常に興味深い。ここ数作、監督は《スマホ》のチャットを見るという行為を如何にアクションにつなげていくかに執着していた。今回、そのアクション技法の研究から離れ、《スマホ》描写はセリフにのみ留めている。その代わり、ヒトとSNS、現実と虚構の間にある価値とは何かについて、議論から答えを見出そうとしているのだ。
まず、「本の価値」という大きなテーマを掲げる。ハードカバーが13ユーロで買えるのに対し、電子書籍はたった3ユーロで買える。その差は単なるコストによるものなのか?というところから始まる。そして、最近のWebの文章は質が向上しているという切り口から、本よりもブログの方が多くの人に読まれているという話に移ろい、情報は無料であるべきか否かの論争になる。そして、その中で、Webの文章はSEO対策(検索した時に自分の記事が上位になるよう、記事に固有名詞を沢山入れる等して対策すること)されているので本とは全く違うという意見が飛ぶ。はたまた、「老人はネット音痴だから紙の本しか読まない」という言及に対して、「寧ろkindleでの本購入者の多くは老人だ」と切り返される。
バカロレアがあるように常日頃から自分の意見を論理立てて相手に伝える。討論を通じて新しい発見をしていくフランス人ならではの白熱した議論の中で、観る者の知的好奇心を揺さぶるトピックスがうごめいているのだ。「テクノロジーは人類に挑戦する」というセリフがあるように、新しい技術によって従来の価値観が瓦解する中で、如何にして折り合いをつけていくのかという話になっていく。そして、これは電子書籍化運動が失敗に終わり、漫画村騒動で出版業界と海賊版との間で軋轢が生じ混沌を極めている日本に住む我々にとって他人事ではない話だと気づかされていくのだ。
ラストが惜しい
ただ、この作品欠点があり、そこが評価の分かれ目になっている。それは、テーマがブレてしまっているということだ。本作は、出版業界のイザコザからモノの価値観を問う話が軸になっており、それだけだと物語的起伏を付けづらいのでアクセントとして、オフビートな笑いを付加した。しかしながら、この笑いの方の話に終盤引っ張られていってしまい、終盤は只の不倫話になってしまう。そして、あれだけ白熱していた議論そっちのけで、アランとレオノール両夫婦の間にあった不倫に対して決着をつける形で映画を終わらせてしまうのだ。だから、人によっては、ただただ話題を広げに広げ、とっ散らかったまま映画を終わらせるダメ映画だと思うことでしょう。現にブンブンも、本作は好きだし大爆笑だったのだが、この点においては不満が残りました。
フランスの生の文化を知らないと、笑いどころが分からなかったり、楽しみ辛いところが多いので日本公開されるか不安ですが、個人的にはこの粗には目を瞑って公開してほしいと感じました。
「何も変えないために全てを変える」という引用同様、本作自体がアサイヤス監督にとって、全てを変えて、彼が芯に持っている問題提起を変えないという彼のフィルモグラフィー上重要な作品なので、配給会社さんどうか日本公開お願いします!!
それにしても…
本作で登場する本のタイトルが、「読ませる気あるの?」と思うほどに無味乾燥していた。『沼地』とか『終止符』とか、『火花』のように作家にブランド価値がなければ売れないようなタイトルだ。それこそ、日本では『コンビニ人間』、『億男』、『夫のちんぽが入らない』、『スマホを落としただけなのに』といったキャッチーなフレーズを付けるのが主流となっているイメージなので、尚更カルチャーショックを受けました。
2019年12月20日よりBunkamuraル・シネマ他にて公開が決まりました。






 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!





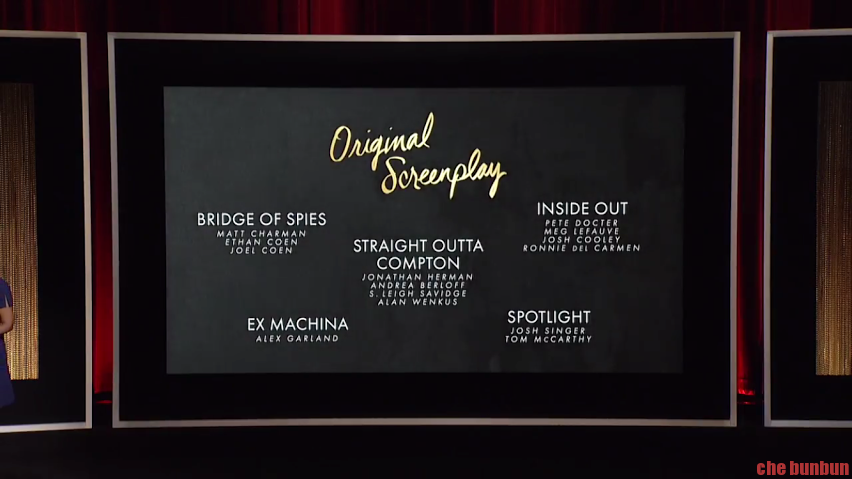


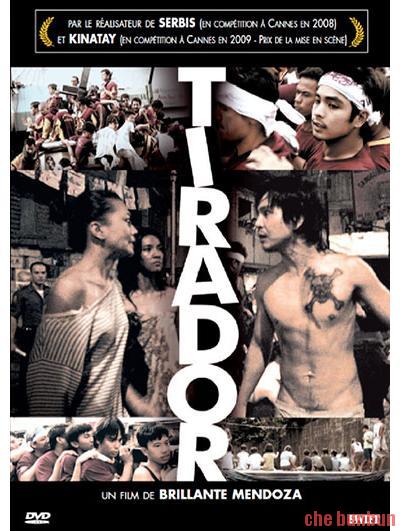







コメントを残す