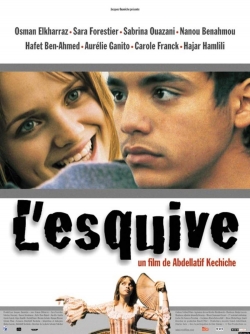ブラックミルク(2020)
原題:Schwarze Milch
英題:Black Milk
監督:ウィゼマ・ボルヒュ
出演:グンスマー・ツォグゾル、ウィゼマ・ボルヒュ、フランツ・ロゴフスキ、テレビシ・デムべレル、ボルヒュ・バワーetc
評価:15点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
第16回大阪アジアン映画祭でモンゴル映画『ブラックミルク』を観ました。本作は第70回ベルリン国際映画祭パノラマ部門で上映された作品。ベルリン国際映画祭は毎年コンペティション部門が批評家からボロクソに叩かれており、ラインナップも地味なので日本公開されないことも多く、また観たとしてもホームランは少なかったりする。
実はベルリン国際映画祭のうまいところはサブ部門にあり、第70回ベルリン国際映画祭ではギリシャのミクロとマクロの閉塞感で挟み撃ちにする『Digger』、肉体の静と動を極端に描いたコンテンポラリーダンス映画『Si c’était de l’amour』、マッテオ・ガローネの気持ち悪さ全開な『Pinocchio』等個性的な作品がサブ部門に出品された。というわけでドイツとモンゴルの合作というユニークなマリアージュにも期待して『ブラックミルク』を観たわけだが、これがイマイチだった。
『ブラックミルク』あらすじ
『そんな風に私を見ないで』(2015)でOAFF2016の《来るべき才能賞》を受賞したウィゼマ・ボルヒュ監督(1984〜)の長編2作目。ドイツで育ったモンゴル人の若い女性ウェッシ(監督自身が演じている)は、20年ぶりに郷里へ帰国し、ずっと離ればなれでいた妹オッシと遊牧生活を始める。姉妹の情が湧くなか、変わり者の男テルビシュをめぐって意見の違いが芽ばえ、自身の欲望に忠実な姉と因襲に囚われた妹の溝が露わになって…。
第70回ベルリン映画祭のパノラマ部門で上映された注目の一作。前作同様、4歳でドイツに移住した監督の実人生に着想を得た内容で、現代のゲル(移動式住居)暮らしを点描しながらも、食と性と死を結びつけ、洋の東西を問わず男性中心にある社会の不条理と、自然と一体に生きられない人間の卑小さを描いている。
排外主義が強まるドイツを象徴する役柄で、フランツ・ロゴフスキ(『希望の灯り』で2018ドイツ映画賞主演男優賞。テレンス・マリック監督作『名もなき生涯』など)が出演。瞬間的な回想や未来叙述、トラウマ的な夢や詩的なヴォイスオーバーを挿入し、21世紀に入っても居場所のない女性たちの優れた肖像を提示している。
※第16回大阪アジアン映画祭より引用
ゲル生活のかけら
ドイツで長年生活したウェッシ(ウィゼマ・ボルヒュ)がモンゴルの妹オッシ(グンスマー・ツォグゾル)のいるゲルに帰郷する。妹は伝統的なルールに従って慎ましく生きるが、そのことでドイツ生活に慣れているウェッシと軋轢が生まれてしまう。監督の自伝的内容なのだが、撮影が難航しているためか断片的ヴィジュアルが並べられているだけだ。本作は恐らく、外国かぶれしてしまいモンゴルの伝統に溶け込めない自分を見つめ直す映画であり、『ブルックリン』のような心理的変化が紡がれることを期待していたのですが、ひたすらゲルの慎ましい伝統を映すだけで、映画祭に来る人のオリエンタリズムを満たすことだけに全振りしているのが致命的だと思う。
世界の秘境、特殊な文化の映画は時に欧米人のオリエンタリズムを満たすことに力点を置いてしまい、肝心な物語が微妙なケースに陥りがちなのだが、本作は完全に撮影の不足をそれでごり押ししている感じがして、観ていて気分が悪くなった。
ウィゼマ・ボルヒュ監督の自伝的映画と聞いて、尚更モンゴルの文化に土足で入っている感じがしてタチが悪い作品でした。一応、大阪アジアン映画祭映画祭で観た映画は全部感想書くことを決めたので、記事化しましたが、本当に書くことが何もない。本祭ワーストです。
※第16回大阪アジアン映画祭より画像引用