ジョーカー(2019)
JOKER
監督:トッド・フィリップス
出演:ホアキン・フェニックス、ロバート・デ・ニーロ、ザジー・ビーツetc
もくじ
評価:65点
おはようございます、チェ・ブンブンです。昨日、ブンブンは『ジョーカー』と『宮本から君へ』を観てきました。どちらも下手すれば心に潜む邪悪な感情を呼び覚まし、自分を蝕みそうな劇薬で、今日紹介する『ジョーカー』は試写の段階から「これは子どもに魅せてはいけない」「これは模倣犯が現れる。ヤバい!」と不穏な風の便りが漂っていました。最近、仕事で精神すり減らしているブンブンが果たして観ていいものなのか?ただでさえ『ザ・マスター』のホアキン・フェニックスのような狂気と暴力性を宿しているのに…と思いつつ観に行きました。
…大丈夫です。精神は正常です。
ただ、金獅子賞を獲ったのは納得のクオリティで、予想に反して面白かったものの、色々と問題を抱えている作品でありました。また、Twitterが『アベンジャーズ』や『スター・ウォーズ』シリーズ以上に盛り上がるのも納得、ポエムな文章で感想を書きたくなるのも納得のちょっとやそっとじゃ、消化できない深みを抱えた作品でありました。というわけで、ブンブンもネタバレありで本作を6つの観点から考察していこうと思う。割といつも以上にとっ散らかった文章になっているとは思いますが、参考にどうぞ…
『ジョーカー』あらすじ
「バットマン」の悪役として広く知られるジョーカーの誕生秘話を、ホアキン・フェニックス主演&トッド・フィリップス監督で映画化。道化師のメイクを施し、恐るべき狂気で人々を恐怖に陥れる悪のカリスマが、いかにして誕生したのか。原作のDCコミックスにはない映画オリジナルのストーリーで描く。「どんな時でも笑顔で人々を楽しませなさい」という母の言葉を胸に、大都会で大道芸人として生きるアーサー。しかし、コメディアンとして世界に笑顔を届けようとしていたはずのひとりの男は、やがて狂気あふれる悪へと変貌していく。これまでジャック・ニコルソン、ヒース・レジャー、ジャレット・レトが演じてきたジョーカーを、「ザ・マスター」のホアキン・フェニックスが新たに演じ、名優ロバート・デ・ニーロが共演。「ハングオーバー!」シリーズなどコメディ作品で手腕を発揮してきたトッド・フィリップスがメガホンをとった。第79回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、DCコミックスの映画化作品としては史上初めて、最高賞の金獅子賞を受賞した。
※映画.comより引用
ポイント1.神話が民話に歩み寄る挑戦
DCとMarvelの違いは神話と民話だという理論は、町山智浩を始めよく提唱される理論だ。スーパーマン、バットマンといったDCのキャラクターは人間離れし、弱みも我々一般庶民からすると中々現実感の湧かないものだったりする。そしてそれに対峙するヴィランもジョーカーやトゥー・フェイスといった超絶個性的なものだったりする。フィクションとしてのキャラクター造形をしている。
一方、Marvelのキャラクターは人間味が溢れている。あのアイアンマンことトニー・スタークですら、莫大な富を得たものの、アベンジャーズという船頭しかいない混沌の中でどのように折り合いをつけて国際平和、宇宙平和を実現するのか悩むあたりに中間管理職、ないし社長の苦悩が滲み出ている。また『スパイダーマン/ホームカミング』や『スパイダーマン/ファー・フロム・ホーム』のヴィランは、トニー・スタークの傲慢さに裏切られ社会の片隅で生きることを余儀なくされたインテリだったりして、ヒーロー/ヴィラン双方のドラマと自分を取り巻く葛藤がシンクロしやすい土壌が築きあげられている。
こういったことから、DCは神話、Marvelは民話という住み分けがされているという理論が導き出されている。
しかし、今回の『ジョーカー』は驚くべきことに、DC映画にも関わらず《民話》に歩み寄ってきたのだ。そして、ジョーカーのファンは起こるであろう、彼最大の魅力である《得体の知れなさ》という敢えて残してある黒いキャンバスに、鮮血と新緑のペンキを塗りたくっていたのです。ジョーカーはニーチェでいう善悪の枠組みとは別次元に行ってしまった超人である。彼は利益を求めず、人が善悪の彼岸で苦しみ、過ちを犯す様子を楽しむだけ。どんだけ痛めつけようと、「何?ジョークにマジになっているの?」と煽り、彼を葬り去ること自体が敗北宣言であることを意味する厄介なヴィランである。ヒース・レジャーのあの邪悪なジョーカーで深掘りされたそのキャラクター像、最大の魅力は、こういった《得体の知れなさ》、概念が具現化したような存在。掴めそうで掴めないキャラクターだった。そこに、「実は彼は病気持ちでねぇ」というペンキを塗るとんでもないタブーを冒している。
そして終いには、この映画はトッド・フィリップスという『ハングオーバー!』シリーズでお馴染みコメディ専門監督が、コメディアンを描いておきながら、一切の笑いを映画の中から消してしまう魔法でもって紡いでいるのだ。
一つ一つが大きな賭けで、即酷評炎上祭に発展しかねない爆弾を抱えている。実際に予告編を観た段階では、非常に不安が残るものだったのですが、これが非常によくできていた。確かに金獅子賞も納得だ。
ポイント2:《悲劇は遠くから見れば喜劇》だに対する反論
トッド・フィリップスがコメディを知り尽くした男だからこそ、この映画におけるコメディの描写が洞察力の塊となっており、一つ一つのディティールに見応えがある。
まず、冒頭。店先で、看板パフォーマンスをするアーサー(後のジョーカー)がその看板をチンピラに奪われた挙句、暴力に負ける瞬間が描かれタイトルが提示される。その次の場面では、アーサーがヒィヒィと泣いているのか笑っているのか分からない表情がアップで長々と映し出される。アーサーのコスプレは《ピエロ》であることを思い出していただきたい。《クラウン》の中でも《ピエロ》だ。ピエロには涙の印が付いている。それはピエロは常に戯け続け、人々にバカにされ、心に傷を負うもののそれを悟られないように涙の印をつけている。つまり悲しみの印なのです。そして物語が進むと、彼は突然笑いが止まらなくなる病気を抱えていることが明らかにされる。
こういった多層的な顔によって、彼は笑っているのか泣いているのか分からない、得体の知れなさが浮かび上がってくる。そうです。単にジョーカーの持つ《得体の知れなさ》を表す黒いキャンバスにペンキをぶちまけているのではなく、緻密に余白を残しているのです。こういった配慮により、ジョーカーファンも最低限満足するところまで物語を底上げし、余計なノイズが入らないよう調整しているのです。
そしてこの多層的な顔を使って、トッド・フィリップスは面白い思考実験を行う。
一般的に、悲劇=主観/喜劇=客観という方程式があり、遠くから見れば悲劇も喜劇だと言われる。では悲劇の渦中にいる人が自ら喜劇に変えられるのか?その瞬間を観客が近い位置で観測できるのか?という問題提起の元、アーサーがジョーカーになるまでのプロセスが描かれる。アーサーは病気持ちだが、コメディアンを目指しながら病気の母親を介護している。しかし、市の政策で定期的に行なっているセラピーも打ち切られ、彼は孤独の淵に立たされる。実は父親は大富豪。ひょっとしたら自分は救われていたのかもしれないという甘い蜜の横で、薬とタバコ、不安に心がグチャグチャになっていき、冷蔵庫に入り自殺しようにも、心が弱いので死ぬこともできない。徹底的に悲劇を魅せていく。それも一つ一つの要素が、すぐ側にあるようなリアルで生々しい実情なので、観客は嫌が応にも主観で事象に対峙する。つまり悲劇の渦中に放り込まれる。
悲劇の渦中に放り込まれた我々観客は奇妙な経験をする。
そして、職も親も金も友人も全てを失った彼は、全てがジョークなんでしょとどうでもよくなる。そして《これは喜劇なのさ》と自分に念じることで、ジョーカーとなり惜しみなく銃を撃つようになる。
本作はコメディ映画職人トッド・フィリップスが《悲劇は遠くから見れば喜劇》なんてもう言ってられないと叫んでいるように見える。ドナルド・トランプが炎上する前に自ら炎上芸を仕掛け、狂人として振る舞うことで喜劇に魅せている。そしてその魅惑の喜劇が、人々の憎悪を呼び覚まし、過激にさせ、差別や断絶を生み出す。喜劇という仮面の下で悲劇が蠢いている。そして、イギリスのEU離脱、デンマークの移民廃絶運動、韓国、香港のデモと混沌が世界を覆っているのだが、それは《喜劇》ではないと監督は笑み無き喜劇で表明したと言えよう。
ポイント3:『キング・オブ・コメディ』、『タクシードライバー』より重要な『ネットワーク』の面影
巷では、『ジョーカー』と併せて『キング・オブ・コメディ』、『タクシードライバー』を観ると良いよと盛り上がっている。確かにロバート・デ・ニーロが出演していたり、個人の一方的な感情の暴走を描いているあたりに共通点を見い出すことができる。しかし、個人的にシドニー・ルメットの『ネットワーク』こそが本作のキー要素だと踏んでいる。『ネットワーク』は1976年の映画で、アカデミー賞主演男優賞、主演女優賞、助演女優賞、脚本賞を受賞した作品。視聴率低下によりクビとなったニュースキャスターが公開自殺をすると番組内で宣言する。すると視聴率が一気に上がり、それを「しめた!」と思ったプロデューサーは、彼を偶像として祭り上げ、世間のヘイトを吐露させ視聴率を上げようとするドラマだ。
実は、本作においてジョーカーは空っぽの偶像として描かれている。彼は殺人を犯したが、彼の正体が明らかになる前に、人々は暴動を始めているのだ。富裕層と貧困層の断絶によって貧困層の人々はヘイトを溜めているが、爆発する機会がない。そこに、ピエロが大企業の職員を殺すという象徴が与えられたことにより、彼らに機会が提供され暴動に至るのだ。
一方、マスコミは番組を盛り上げようと、観るも病気なアーサーを祭り上げる。テレビの司会者は、外で暴動が起きる中、ピエロのコスプレをするアーサーを、「視聴率が稼げるかもしれない」という浅はかな気持ちでそのまま出演させてしまう。そして、彼らはしっぺ返しを受ける。滑稽無形に振舞っていたアーサーは「世界なんか壊れてしまえばよい!」と殺人の告白をする。そして、憧れのテレビの司会者と対話をする内に、司会者は所詮安全な箱から下界を見下しているんだということに気づき、怒り、彼を射殺してしまう。それと同時に世界は、マスコミの、大企業の欺瞞に怒りを爆発させ暴動がさらにヒートアップしていくのだ。これは『ネットワーク』の裏返しとも言える展開だ(『ネットワーク』のネタバレになってしまうので、興味ある方は是非観て確かめてください)。
詰まる所、本作は人が狂人になるプロセスよりも、断絶によって生じる見下しの目線、あるいは安全地帯から下界を覗き込む視点の危うさに重点を置いた作品なのではと捉えることができ、仄かに匂わせる『ネットワーク』に演出の鋭さを感じます。
ポイント4.ジョーカーのズレた笑いのカルト性とコウメ太夫の意外な関係性
涙が止まらないと思ったら~、
ウォシュレットおしり貫通してました~。
チクショー!! #まいにちチクショー
— コウメ太夫 (@dayukoume) October 4, 2019
人間が生理学的欠陥を有する生物である事を指摘し、人間を「欠陥動物」と定義したゲーレンによれば、人間はそれ故に抽象的操作や文化創造を行ったのだという。「高品質なソニ〜製品」を創り出すソニ〜所属の小梅氏は、ゲーレンの議論を受け、高品質の商品に対し、我々は“欠陥品”であると宣言するのだ。
— 哲学者コウ・メダユー (@koume_philo) September 28, 2019
ところで、テレビ司会者が考察する、笑い続ければ、人々は思わず笑ってしまう。彼こそがジョーカーだ。という理論を体現している芸人が日本にいる。それはコウメ太夫だ。白塗り、甲高い声で、つまらないギャグの後に「チクショー」と叫ぶ前のめりな演出は、2000年代バラエティ番組『エンタの神様』で一瞬話題となり一発屋として消えた…と思われた。しかし、コウメ太夫はTwitterで《まいにちチクショー》と称し、毎日捉えどころのないギャグを連発し続けていた。その独特な世界観が人気を博し、哲学的側面から分析する者、いらすとやのイラストで事象を再現する者、英訳してみる者と様々なフォロワーが増えていき、カルト化していった。『ジョーカー』のクライマックスで、ジョーカーは精神分析医に「(俺のギャグは常人のお前には)分からないさ」と言い捨てる。ジョーカーの一般人と違った笑いどころを開き直り、無視していくスタイルとコウメ太夫の一貫した異次元のユーモアは近いものを感じます。
日本で『ジョーカー』をリメイクするのであれば、是非ともコウメ太夫に挑戦して欲しい。個人的に応援している芸人なだけに、全く関係ないのですがここで応援してみました。
ポイント5:『パラサイト 半地下の家族』と併せて2019年映画界が変わった
2019年は2010年代の終わりという節目年でああるが、映画史の観点で一つ面白い傾向が見えた。それはカンヌ国際映画祭最高賞を獲った『パラサイト 半地下の家族』と『ジョーカー』は全く同じベクトルを向いていたのです。それは、1に社会の断絶を描いている。2にエンターテイメントとしてのバランスが確保されている。3にアート映画としての魅力もあるということだ。特に2010年代のカンヌ国際映画祭最高賞というのは正直酷いと思う。一般的に映画祭というのはアカデミー賞とは違い、少数の人数で賞を決めるというもの。少数故に、普段あまり注目されない作家や、アート性が強い作品にスポットライトが当たりやすくなる。寧ろそれが映画祭の役割である。しかしながら、カンヌは安直な弱い人にスポットライトを当てたリアリズム重視な作品ばかりを最高賞に選んでいる。確かに『アデル、ブルーは熱い色』や『万引き家族』は良い作品だが、果たしてそれで良いのか?特に、カンヌの場合は、フランスの中でも物価が高いリゾート地で行われ、映画関係者であっても階級で注目作が観れたり観れなかったりする場所。そこで弱い人の映画を手放しに褒めるのは、ある意味欺瞞だと言えよう。高みから見下しているようで嫌な感じがする。
しかし、今回パルムドールを獲った『パラサイト 半地下の家族』も金獅子賞を獲った『ジョーカー』も一見2010年代的弱き人に手を差し伸べる系映画の皮を被っておきながら、その素顔は、高みから見下す人に対する鋭い批判となっている。前者は階段/段差の死角でそれを象徴し、後者はスタジオの中/豪邸の中から出ない成功者という視点から皮肉っている。そしてこの手の映画祭最高賞を獲る映画は、問題を声高らかに叫ぶだけで大衆娯楽映画のようなエンターテイメント性が弱かったりするのだが、どちらも観ていて面白い描写が沢山詰まった作品に仕上がっている。それでもって幾らでも深読みできるアート映画的難解さもあるのだ。
これは2010年代映画界が進化したところでしょう。社会問題を描きつつもエンターテイメントとして面白く、アート性もある。理想の映画のカタチを両作が示してくれました。
ポイント6:これは残念!この映画にバットマンの過去は要らない
こう、ズラズラ語っていきましたが個人的に乗れなかったところがある。そしてここがトッド・フィリップスの妥協点であろう。私が、この映画を観てイマイチ乗れなかった。というよりかは興醒めしてしまったポイントとして、バットマンことブルース・ウェインのエピソード0をこの映画の中でやってしまっていることだ。大富豪トーマス・ウェインが実の父親だと知ったアーサーは豪邸まで行く、そこで若かれしころのブルース・ウェインと会ったり、終盤ジョーカーのパフォーマンスによって暴徒化した市民がブルース・ウェインの両親を殺す場面がサービスとして描かれるのだが、正直この描写は不必要だと感じた。
なんたって、本作はバットマンシリーズという領域を超えて、一人の男が狂人になる過程を描いた話だ。ひょっとすると、「自分がコミックスに出てくる《ジョーカー》であると思い込んだ男の妄想」として深読みすることが可能だ。敢えて自分をコミックのキャラクターと思い込む描写を排除することで、スクリーン外で「自分がコミックスに出てくる《ジョーカー》であると思い込む」という現象を引き起こし、本作はフィクションでない、今そこにある危機であることを主張しようとしているのではと考えることができるし、その方が非常に鋭い映画だと思うのだが、ブルース・ウェインを登場させることで、一気にアメコミ映画を超えて世界に革命を起こそうと飛躍しようとしている本作の足枷となってしまっている。もしかすると、本当に飛躍してしまうと、世界がジョーカー信者の支配下になってしまうことを恐れたのか?この映画はジョーカーがロバート・デ・ニーロ演じるテレビの司会者を射殺した後、ダラダラと《ブルース・ウェインがバットマンになるまでエピソード0》をやってしまう。
個人的には、司会者を射殺し、ジョーカーがカメラを覗き込んだところでThe Endとした方が締まりと深みがあって良いのではと思ってしまった。
最後に…
本作は、2019年最大の問題作であり、アカデミー賞の前哨戦であるヴェネチア国際映画祭で最高賞を受賞した。おそらくは、アカデミー賞作品賞、監督賞にノミネートするでしょう。また、『ザ・マスター』に匹敵する狂気を宿したホアキン・フェニックスの演技は『容疑者、ホアキン・フェニックス』で業界から嫌われた汚名を拭い去り、遂に主演男優賞を獲得するのではと予想している。Marvelばかり輝いてなかなか陽の目を浴びなかったDC。個人的には理論としては面白いが、そこまで傑作とは思わないものの、今年最も応援したい映画の一つと言えよう。P.S.実はジョーカーよりも『宮本から君へ』の宮本の狂気の方が怖かったですよw














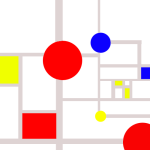









コメントを残す