『デカローグ』フルマラソンしてみた
今年はインド映画とポーランド映画に力を入れるといっておきながら、なんだかんだ全然ポーランド映画を観ていない。むしろフィリピン映画の方が観ている事実に焦燥を感じた。丁度、そんな中、クシシュトフ・キェシロフスキのテレビシリーズ『デカローグ』を全巻揃えることができたので観てみました。本作は、『ふたりのベロニカ』やトリコロール三部作で有名な鬼才・クシシュトフ・キェシロフスキ1989年から1990年にかけて製作したテレビシリーズだ。しかし、あまりの完成度の高さから、『死ぬまでに観たい映画1001本』に掲載され、さらに全10話のうち、《ある殺人に関する物語》《ある愛に関する物語》は長編映画化もされた。そんなテレビシリーズを数日に分けて観たのだが、どれも魅力的な物語でした。今回は全10話中5話まで短評を載せていきます。
第1話 ある運命に関する物語
1話にして最高傑作。唯物論者寄りの教授と、その息子の話だ。教授は大学で論理学を教えている。そして、息子にパソコンを与え英才教育を施している。息子は、ラズペリーパイもない時代なのに、扉や蛇口を自動制御できるプログラムを開発する程優秀で、父の血を継いでいる。そんな息子が、雪道で死体を目撃したことから、論理的に解決できない不思議なことが起こるという話だ。
本作は、教授、論理学、コンピュータといった、論理的、合理的象徴が画面を包み込むことから始まる。しかしながら、そんな象徴の一つコンピュータからどんどん合理性が失われていき、神のような存在になっていく。結局、ヒトという生き物は、人智を超えたものを観たときにそれは神のような感情的存在として消化するしかないということをキェシロフスキは観客に突きつけた。シンプルながらも底が見えない程に奥深い作品であった。
第2話 ある選択に関する物語
2話目は苦渋の選択にまつわる物語だ。夫が危篤となっている中、妻は夫の親友である父と中絶するか否かを討論する話。まるでマイケル・サンデルの白熱教室の内容を映画化したような作品。1話目が強烈すぎた為か、あまり言いたいことはない。
第3話 あるクリスマスイヴに関する物語
ジャン・ユスターシュ『サンタクロースの眼は青い』に次ぐ隠れたクリスマス映画の傑作。クリスマスイヴの日にサンタクロースのコスプレをして、子どもたちを喜ばせようとするタクシー運転手の元に、昔の彼女が現れ、一晩過ごすこととなるのだが、その彼女が無理心中しようとしてタクシー運転手がパニックパニックになるというトンデモ映画だ。どうしたらこんな陰惨なクリスマス映画ができるんだ?というほどにシュールで悲惨で不条理すぎる展開、そして恍惚とは程遠い毒々しい赤の光に魅せられました。
第4話 ある父と娘に関する物語
仲良しこよしの娘と父親。しかし、父親が実の父親ではないと知り、娘が男として父を愛するようになるという話。ヒトは究極までに因数分解すると、結局《男》と《女》になる。恋愛も所詮男と女の関係に過ぎないが、そこに社会規範や常識、道徳が加わることでいかに厄介な事態へ陥るかを綴った物語。そこまで面白くはない。
第5話 ある殺人に関する物語
あまりのレベルの高さに長編映画化もされ、その長編映画がカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞した傑作。本作は、『ダンサー・イン・ザ・ダーク』に多大な影響を与えたといっても過言ではない。青年が殺人を犯すまでの過程を、汚く荒々しい色彩で生々しく描き、そして死刑が執行されるまでの心の揺らぎを緻密に描いていく。とにかく、少年がタクシー運転手を絞め殺すまでの過程は素晴らしく、これを観てしまった後に別の映画を観ても薄味にしか感じなくなってしまいます。

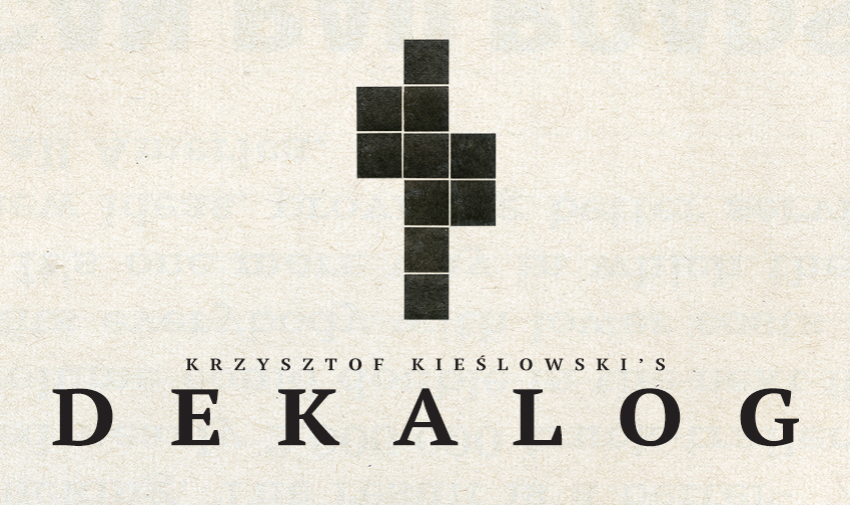



 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!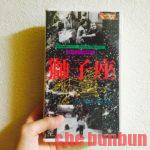

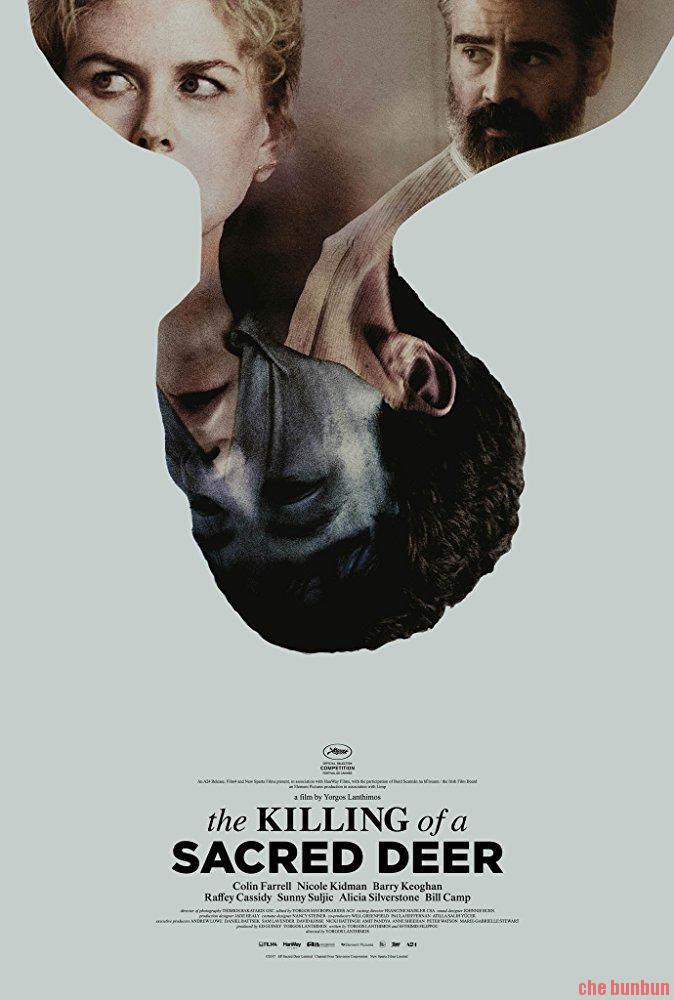





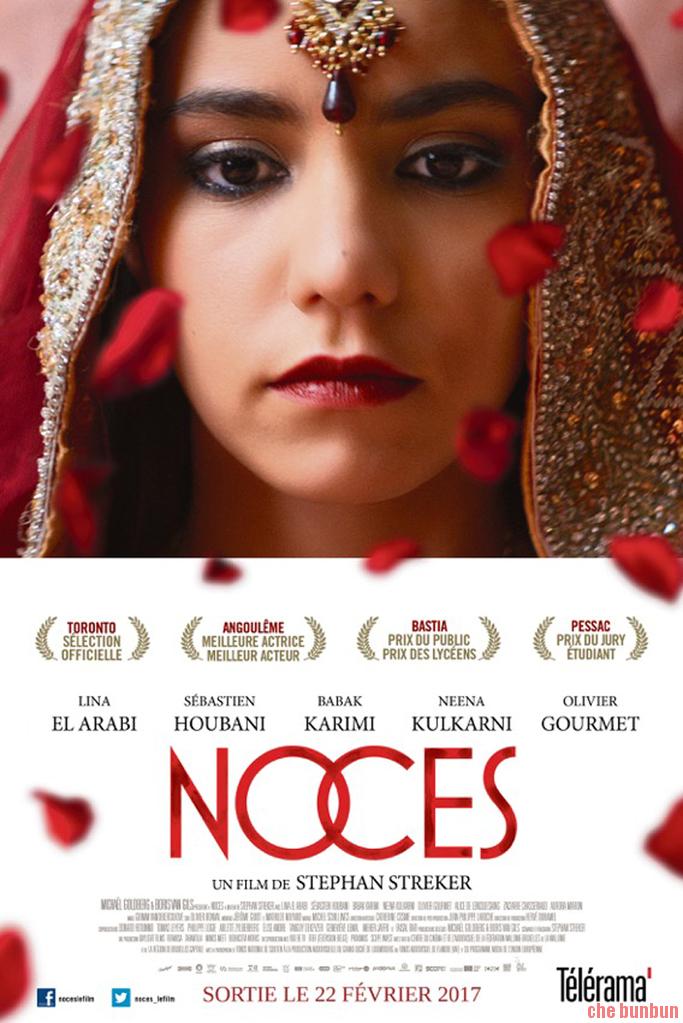








コメントを残す