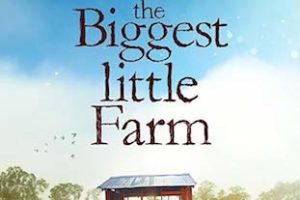ミセス・ノイズィ(2019)
Mrs. Noisy
監督:天野千尋
出演:篠原ゆき子(篠原友希子)、大高洋子、新津ちせ、長尾卓磨、宮崎太一etc
評価:50点※ラスト除けば100点です
おはようございます、チェ・ブンブンです。
2020年の追い込みで新作映画を片っ端から観ている師走の私。映画仲間から、「ブンブンさんは好きかもしれないよ」と言葉濁した形でオススメされた映画がある。それが『ミセス・ノイズィ』だ。第32回東京国際映画祭で密かに話題となっており、今年の初めくらいに映画ライターのヒナタカさんが絶賛していた作品。「騒音おばさん」の名でインターネットカルチャーとなった奈良騒音傷害事件の映画化らしいのだが、想像する内容と違うらしい。というわけで観てきました。確かに多くの人が語るように、未見の人にはほとんど語れることがない映画なのでネタバレ記事とします。
『ミセス・ノイズィ』あらすじ
「フィガロの告白」の天野千尋が監督・脚本を手がけ、隣人同士の些細な対立が大事件へと発展していく様子を描いたサスペンスドラマ。小説家で母親でもある吉岡真紀は、スランプに悩まされていた。ある日、突如として隣の住人・若田美和子による嫌がらせが始まる。それは日を追うごとに激しさを増し、心の平穏を奪われた真紀は家族との関係もギクシャクしていく。真紀は美和子を小説のネタにすることで反撃に出るが、その行動は予想外の事態を巻き起こし、2人の争いはマスコミやネット社会を巻き込む大騒動へと発展していく。主人公の小説家・真紀を「共喰い」の篠原ゆき子、隣人の美和子を「どうしようもない恋の唄」の大高洋子、真紀の娘を「駅までの道をおしえて」の新津ちせがそれぞれ演じる。2019年・第32回東京国際映画祭「日本映画スプラッシュ」部門出品。
※映画.comより引用
岡目八目だと思う盲者たち
本作は10年に1本観るか観ないかの珍しい作品だ。
というのも最後10分までは満点の大傑作にもかかわらず、最後の最後で大暴投を放ってしまうトンデモ映画だったからである。主人公一家は、アパートに移り住む。妻の吉岡真紀(篠原ゆき子)は、成功した小説かであるが、ワンオペ子育てに疲れ切っており、すっかりネタが枯渇してしまった。それを認められなくてとにかく書いて、書いて、書いて出版社に赴くもあまり成果を得られていない境遇だ。しかし、夫・裕一(長尾卓磨)はのほほんと家事・育児もどきのことをやって全然事態の深刻さに気づいていない。娘・菜子(新津ちせ)は、父も母も構ってくれなくて退屈でフラストレーションを抱えている。そんな不穏な状態から物語は始まる。引越しの整理がついていない状態で真紀は執筆に励んでいる。娘に「遊ぼうよ」と絡まれるが、邪険に扱ってしまっている。そんな中、朝5時にもかかわらず、バコンバコンと何かを叩く音がする。恐る恐る見ると、隣人が狂ったように布団を叩いているのだ。彼女が注意すると、「んもう、もう終わるよ!」と不機嫌そうだ。
そんな不快感はジワジワと蓄積されていく。母が遊んでくれないもんだから外に飛び出した娘は、その隣人と遊んで帰ってくるのだ。既に不信感ある母は、隣人と諍いを起こす。ただ、娘は隣人を良い人だと思っており、別の日には家にまで遊びに行ってしまうのだ。そして、娘の口から隣人の夫と風呂に入ったという言葉を聞いてから怒りが爆発する。
出版社からは「あんたは休んだ方が良い。根本的に薄い。」と言われ、夫からは「ヒートアップしすぎだ」となだめられ、娘からは隣人は良い人だと言われ、孤独な彼女はフラストレーションが火山のように噴火しそうだ。そこに、親戚から悪魔の囁きがあり、隣人をネタにした小説を書くことにする。
通常の映画であれば、家族の中で家事・育児するだけの存在となった女性の抑圧にフォーカスをあてて、彼女の視点だけで描くであろう。しかしながら、本作の面白いところは隣人の目線が描かれることで、全てを知ったつもりになってしまっている観客に問題提起をする仕掛けとなっている。
隣人のおばさんには夫がいるが、精神障がいを抱えており、見えない虫に悩まされている。朝になると悲鳴をあげるものだから、彼女は布団を叩く。大きく叩くことで夫を安心させようとしているのだ。また、真紀に注意された際も丁寧に事情を説明しようとしている。だが、真紀目線のパートでは、その説明しようとしている姿をバッサリと切り捨ててしまっているのだ。だから、我々が観ていた視点は、彼女が同情を誘うように都合よく切り取られた景色だったのです。そして隣人目線から、諍いを見ると明らかに真紀が菜子に対してネグレクトしているようにしか思えないのだ。だが、そう簡単に天野千尋監督は隣人に同情させるような作りにはしない。彼女も、表面上だけで「ペンネームなんて馬鹿馬鹿しい」と嘲笑っており、小説家の仕事を理解しようとしないのだ。
この全て知った気になって、何も知らないというところが本作のポイントである。
真紀は怒りに任せて小説「ミセス・ノイズィ」を書き上げる一方で、それを出汁に一儲けしようとする親戚が現れる。彼が、二人のベランダ越しの喧嘩を盗撮し、動画投稿サイトで配信することにより、バズるのだ。世間は「ミセス・ノイズィ」と現実とをリンクさせ面白おかしくもてはやす。出版社も次々と彼女にオファーし始めるのだ。だが、ネット文化として消費されたことにより、隣人の夫が心を痛めて、飛び降り自殺を図ったことにより事態は一転する。
マスコミは掌を返したように真紀をバッシングし、騒音おばさんとなった隣人をヒーローとして崇める動画が拡散するようになるのだ。あれだけ証拠集めたら勝訴できますよと言っていた弁護士も、コロッと「名誉毀損で訴えられるし、ほぼ負けるでしょう」と意見を変えてしまうのである。結局、世間は物事の一部しか観ておらず、社会の波に応じて付和雷同なだけであることを立体的に描いているのだ。リューベン・オストルンド映画のようにとことん意地悪で、まさしくキム・ギドクの追悼を巡り「追悼した奴も有罪」とか「パワハラ・セクハラ問題について映画人はなんかコメントしろよ」と、正義を振りかざし暴力的な形で他人の意見を変えさせようとするくせに、『DAU.ナターシャ』の問題には全然向き合おうとしなかったり、アップリンクやユジクのパワハラ問題に関して炎上させるだけ炎上させておいて時間が経つと風化してしまっていたりする2020年を象徴するような作品でありました。
ただ、、、残念なことに、天野千尋監督には意地悪を突き通す度胸がなかった。
何故か、本作は「いい話」として着地しているのだが、その選択があまりにも邪悪である。
結局、隣人の夫は一命をとりとめた。そして、家族は世間体を考慮して引っ越すのだが、何故か加筆修正した小説「ミセス・ノイズィ」を隣人に送りつけるのだ。夫が死の淵に瀕する程精神的ダメージを与えたのに、マスコミ相手に少し呉越同舟になったからって騒動の小説を送りつけるなんて非常識である。にもかかわらず、この映画では美談として、笑い話として描いてしまっているのだ。また冷静沈着を保ってながら、自己中心的な夫は終盤で妻を見捨てる。そしてラストシーンでは、妻のことを振り向いてくれなかった夫に後光を差し込ませ、まるで神に妻が赦しを求めるのだが、そもそも本質的な原因は夫にあるのだ。夫が家事や育児を面倒見て、妻の気持ちを慮れば、騒動は起きなかったはずなのである。朝5時の布団叩き、家にいてもおかしくないのに一度も隣人とのトラブルを見ていない夫を聖人にするとはどういうことでしょうか?夫の無関心を強調して起きながら、いきなり良い人にしてしまうラストにすっかり興醒めしてしまいました。
なんなら、定食屋のシーンで、スマホに暴言が沢山送りつけられ、妻が孤独に押しつぶされそうなところで終わりにし、徹底的に突き放した方が傑作になったと思います。なんて勿体無い映画なんだろうか。そしてこれを観て、自分の意見という手綱を他者に委ねてはいけないなと強く思うのでした。
※映画.comより画像引用