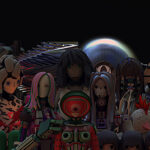バーフライ(1987)
BARFLY
監督:バルベ・シュローデル
出演:ミッキー・ローク、フェイ・ダナウェイ、フランク・スタローン、J・C・クイン、アリス・クリーグ、ローラ・ダーンetc
評価:90点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
“101 CULT MOVIES:YOU MUST SEE BEFORE YOU DIE”に掲載されている『バーフライ』を観た。本作は、私が敬愛する作家チャールズ・ブコウスキーが脚本を手がけている作品でもある。チャールズ・ブコウスキーといえば「映画嫌い」で知られており、「死をポケットに入れて」でボヤいていたイメージが強い。そんな彼が映画の脚本を書くとどうなるのだろうか?実際に観てみた。
『バーフライ』あらすじ
ロスの場末の酒場“ゴールデン・ホーン”には様々な人間がたむろしている。感性の鋭い若き作家ヘンリー・チナスキー(ミッキー・ローク)もその中の1人。彼は社会の歯車に組み込まれるのを拒んで酒に明け暮れ、気がむけばペンを走らせる。酒を呑み、バーテンのエディ(フランク・スタローン)と殴り合いばかりしている毎日だ。そんなある日、ワンダ(フェイ・ダナウェイ)と知り合う。彼女も人生に幻滅感を抱いて酒に溺れる毎日だった。恋とは無縁の2人だったが恋におち、共同生活を始めるようになった。そんなヘンリーの周辺を調査する私立探偵の姿があった。依頼主はタリー(アリス・クリッジ)という女。彼女は雑誌のオーナーで、彼の才能に目をつけ、現在の悲惨な状況から脱け出させ、執筆に必要な資金と環境を提供しようと申し出た。だが、ヘンリーにとっては、現在の生活以外考えられず、彼女から前渡し金として受け取った500ドルをバーの仲間に酒をおごってつかい果たしてしまった。タリーはいつの間にかへンリーに愛情を抱いていたのだが、所詮、住む世界は別なのだ。タリーは自分に敵意をむきだしにするワンダとつかみあいの大喧嘩の末、2人の前から去っていった--。ワンダとなじみの酔客とともに酒をくみ交わし、エディに喧嘩を売り、今日もヘンリーの夜が更けていく。
社会の歯車から外れた男は自宅とバーを往復する
『バーフライ』はチャールズ・ブコウスキーの私生活そのものである。社会のレールから外れた者が部屋とバーを往復する。バーで飲み明かし、部屋では詩を書き殴る。そんな日常を映画として切り出している。おそらく、ブコウスキーは物語らしい始まりと終わりを決めなくてはいけない点で映画を嫌っていたのだろう。本作において、主人公は何も成長しなければ何も変わらない。ひたすら虚無の日常が続く。それを喧嘩が始まるバーで始まりバーで終わる円環構造で閉じることで表現している。なので、ブコウスキーの本を愛する者にとっては、文字の並びで想像していた世界がそのまま提示された世界観に酔いしれるであろう。一方で、バルベ・シュローデルの手腕によって映画的ではない物語に映画的要素が付与されている。たとえば、探偵がヘンリー・チナスキーの部屋に侵入する場面がある。ヘンリーは、トイレを探すかのように外へとふらつく。その隙に探偵が入り、詩を写真に収めていく。次の場面でヘンリーの移動が映されるのだが、彼と探偵のショットでは共通した音楽が流れている。それにより、ヘンリーが部屋へと戻ろうとしていることが分かりバレるかバレないかサスペンスとしての盛り上がりが生じる。ヘンリーが、力づくで部屋に入ると誰もいない。実は別人の部屋である。修羅場映画における、一難去ってまた一難がここで起こる。なぜならば、まだ探偵は部屋にいるからだ。再び、ヘンリーが部屋へと戻る。ギリギリのところで探偵は階段を降り去っていくのだ。アンニュイな世界が続く中で、スパイスとしてこの手のサスペンスを織り交ぜていく。ワンダとの逃避行、バーで発生する一触即発の戦い、煽り運転などが刺激として映画を魅力的なものへと押し上げていくバルベ・シュローデルの手腕に感銘を受けたのであった。
※MUBIより画像引用