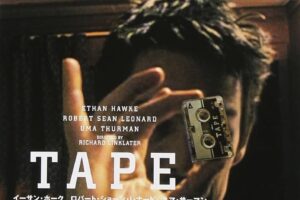広島を上演する(2023)
監督:三間旭浩、山田咲、草野なつか、遠藤幹大etc
評価:60点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
東京フィルメックスで上映された広島をテーマにしたオムニバス『広島を上演する』を観た。日本のインディーズ映画は、行間を語りや空間によって表現するのに長けた作品が多いのだが、本作ではそれぞれユニークなアプローチから現実、虚構、歴史を紐解いていっており興味深かった。
「しるしのない窓へ」▶︎60点
「ヒロエさんと広島を上演する」▶︎20点
「夢の涯てまで」▶︎70点
「それがどこであっても」▶︎90点
『広島を上演する』あらすじ
4人の若手監督が広島をテーマに描いたオムニバス映画。
演劇カンパニー「マレビトの会」が、舞台作品「長崎を上演する」「福島を上演する」に続き、被曝都市である広島を題材に映画作品として制作。これまで「マレビトの会」の作品に劇作家や俳優として参加してきた4人が監督を務め、広島の現在を多角的な視点で切り取った。
広島市内のアパートでパートナーと暮らす女性が友人と川辺で詩を共作する姿をつづった三間旭浩監督作「しるしのない窓へ」、原爆投下時に爆心地から約1キロの場所で胎内被ばくした女性がカメラに向かって語る山田咲監督作「ヒロエさんと広島を上演する」、大切な存在を失った女性が喪失と向き合いながら日常生活を送る姿を描く草野なつか監督作「夢の涯てまで」、ある劇団が広島についての演劇作品のリハーサルをする様子と、その作品に音響フタッフとして参加する難聴の青年が野外で音を採取する姿を追う遠藤幹大監督作「それがどこであっても」の4編で構成。
媒介を通して見つめる世界
最初の2編、「しるしのない窓へ」「ヒロエさんと広島を上演する」は明確に対となっている。川辺からアパートへと眼差しを向ける。アパートの部屋と部屋は無個性に見える。だが、語りによってその内部の生活へと歩み寄る。丸縁の画、仄暗い中で『ジャンヌ・ディエルマン』のような冷たさを持った生活が紡がれていく。一方で、「ヒロエさんと広島を上演する」ではアパートから広島の街へと眼差しを向ける。そこへ戦争時の壮絶な体験の語りを乗せていき、美しく平和な街の風景と対位法的関係性を築き上げていく。後者に関しては、いわゆるクロード・ランズマン的アプローチであるのだが、いかんせん画が乏しすぎて退屈に感じる。ランズマンの場合、重々しい土地の空気感の中、被写体の表情を捉え続けることにより、より想像力が掻き立てられるものとなっているのだが、ここでは顔が一切提示されず風景に語りを乗せていく。これがあまり上手くいっていないように感じた。
「夢の涯てまで」では喪失による浮遊感といった抽象的なものを画として具体的に浮かび上がらせるのに長けた一本に仕上がっていた。「広島へ行ったが、何も見つからなかった」という紙に記された独白。不自然な眼差しにさらされるまま、主人公は彷徨う。本屋で広島に関する本を求める。実際に足を運ぶことが解決に繋がらなかった場合、その地に関する文章を通じて再度擬似的に旅へ出ることで解決へと繋げることが可能なのだろうか?映画は簡単に答えは出さない。誰かの気配を感じる夜と昼、そして実際の場と読むことによって生まれる場を通して自分の落とし所を探そうとする様に感銘を受けた。
そして思わぬ大収穫が、最後の「それがどこであっても」である。演劇パートとASMR用のダミーヘッドを使って音を採取するパートに分かれている本作は異様に惹きつかれるものがあった。冒頭、演劇の練習が行われるのだが、不自然に扉が外へと開かれている。外部から、ぎこちない演技が見られる状態の中、身体表象によって状況が生み出されていく。観客は役者を凝視することによって共犯関係的に虚構が生み出されていく。同時に収録パートではダミーヘッドを使って現実の音を捉えていく。何気ない音に対して凝視を行うことになる。それはその土地を知ろうとする運動であり、実際に銃声の音が忍び込み、独特な真実が紡がれていく。この4編共通して描かれる媒介を通して現実や虚構、歴史と向き合うテーマを演劇と音探しを結びつけて語ってみせるアプローチに衝撃を受けたのであった。遠藤幹大監督は今後注目していきたいところである。
※映画.comより画像引用