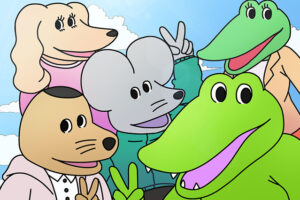ビーンズ(2021)
Beans
監督:トレイシー・ディアー
出演:Kiawenti:io,Paulina Jewel Alexis ,Violah Beauvais etc
評価:65点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
先日、なら国際映画祭オンライン配信で、『地球よとまれ』、『フロム・ザ・ワイルド・シー』、『ラ・ミフ 家族』、『Last Days at Sea 少年の最後の夏』そして『ビーンズ』の5本を観た。この手の小さな映画祭は思わぬ発見の宝庫であり、昨年はスロベニアの『栗の森のものがたり』が印象的であった。今回5本パックを購入し、観たのだが『ビーンズ』以外は微妙だったので、ここに軽く感想を書いておく。
『地球よとまれ』は思春期の男女のモヤモヤを捉えた作品。時折、インタビューシーンが入り、登場人物が心の内を吐露する演出が特徴的だ。また。思春期の孤独の表象として、自分のバトミントンラケットを渡す→男の子が友人とバトミントンをするが強風で一人バトミントンになってしまうのを眺めるというユニークな演出をとっているが全体的にかなり退屈。ところで、ヨーロッパの青春映画は、主人公の心理的距離感を表現するのにクラブを使う傾向がある。日本の場合、何がクラブ描写に当たるのだろうと考えてみた。個人的に文化祭の準備描写やバックヤードがそれにあたる気がする。『サマーフィルムにのって』を例に取れば、文化祭直前に学校で映像編集をする場面がそこにあたる。ライバル同士が編集の合間に会話をする。そこには静けさがあり、自分の内面が流れ出る。ヨーロッパでは、栄えている空間に孤独感や虚無を織り交ぜることで内なる自分を描く舞台装置としてクラブがあるが、日本では文化祭周辺にそれはあったと思った。
『Last Days at Sea 少年の最後の夏』は終わりゆく漁村の運命を捉えたドキュメンタリーだ。亡くなった祖母の料理の味がもはや再現できなくなり、忘れ去られようとしている。村民は何かもう諦めたような表情を魅せる。少年は高校がないので村を離れようとする。そんな漁村の終焉を美しく捉える。正直、ホームビデオの域を出ない。村人にとっては非常に重要な話だ。自分たちの中から消えてしまうものを掴もうとする焦燥がそこにはある。だが、それが外に向いているのか?ドキュメンタリー映画として外へ訴えかけるものがあるかと訊かれたら微妙かな。
『フロム・ザ・ワイルド・シー』はCPH:DOXでも上映されていた海洋ドキュメンタリー。動物保護団体シール・レスキュー・アイルランドの活動に主軸を置いている。自然に返すのだから甘さは要らない。時には眼を摘出した状態で海に返したりする。ショッキングな映像でストイックな活動を伝えるタイプだ。それだけって気もして映画としてはイマイチだ。
『ラ・ミフ 家族』はケアホームで共同生活する者をドキュメンタリータッチで撮った作品。親のネグレクト、虐待から逃げるようにケアホームに入ったが、そこでもどこか居心地の悪さがある時間が延々と続く。どっと疲れた。
では、『ビーンズ』はどうだろうか。
『ビーンズ』あらすじ
Based on true events, Tracey Deer’s debut feature chronicles the 78-day standoff between two Mohawk communities and government forces in 1990 in Quebec.
訳:1990年にケベック州で起きた、2つのモホーク族コミュニティと政府軍との78日間に及ぶ睨み合いを、実話に基づいて描いたトレーシー・ディアの長編デビュー作。
※IMDbより引用
少女の瞳に映る「眼には眼を」
カナダ社会もアメリカ同様、先住民を排除したりアイデンティティを剥奪してきた歴史がある。イヌイットの場合、カナダ政府が保護し、居住区を用意した。そして子どもたちに英語教育を行った。その結果、イヌイットの文化が徐々に失われていくこととなった。ザカリアス・クヌク監督は、消えゆくイヌイット文化を守るため、映画会社を設立し、イヌイットのイヌイットによるイヌイットのための映画を制作することで口承の側面が強いイヌイット文化のアーカイブを行った。
さて、1990年にケベックで発生したオホーク族とオカ町の住人との間で発生した紛争「オカの闘い」はどうだろうか。オホーク族の権利を踏みにじるオカ町の人々に対し、オホーク族が銃で威嚇したことにより紛争へ発展した。
『ビーンズ』はその紛争を子どもたちの目線で描いている。主人公『ビーンズ』は、オホーク族ながらオホーク族のコミュニティ外の学校に通おうとしている。気弱な性格もあってか、オホーク族の不良集団に絡まれたりして居場所がない。そんな彼女の周りで差別の魔の手が忍び寄る。紛争が発生すると、買い物に行っても店員や客に追い出されて何も買うことができない。町を歩いたり、車で走っているだけで石を投げられたりする。
大人たちの醜悪な憎悪はビーンズの心を蝕み、彼女の暴力性を引き出す。オホーク族の不良集団と仲良くなり、ゲームセンターに行くとオカ町の人が見ているのに気づき、「何見ているんだ」と暴行を働くのです。「眼には眼を」と言わんばかりに。
大人たちの強烈な差別を前に何もできないのなら、暴力は正当化されるべきではと短絡的に考えてしまう過程がリアルに描かれており、こういう映画こそ中高生に観てほしいなと感じた。
なら国際映画祭一番のアタリ作品である。