血ぬられた墓標(1960)
原題:La Maschera del demonio
英題:Black Sunday
監督:マリオ・バーヴァ
出演:バーバラ・スティール、ジョン・リチャードソン、イヴォ・ガラーニetc
評価:80点
おはようございます、チェ・ブンブンです。『死ぬまでに観たい映画1001本』には幾つか原作が同じ作品が収録されている。
一番有名なところで言えば『郵便配達は二度ベルを鳴らす』のルキノ・ヴィスコンティ版とテイ・ガーネット版だろう。どちらもジェームズ・M・ケインの同名小説が原作である。前者はヴィスコンティの処女作でありながら、原作無断使用により上映禁止処分となり、1976年ニューヨーク・フィルム・フェスティバルまで30年以上封印されていた作品。それに対して後者は正式な映画化でありフィルム・ノワールの傑作として名高い。さて、この両作は邦題が一致しているため、原作が同一であることが分かるのだが、中には気づかれにくいものもある。アンソニー・バージェスの『時計じかけのオレンジ』がスタンリー・キューブリックだけでなくアンディ・ウォーホルも『ヴィニール(1965)』という題で映画化されていた件なんかはその代表と言えるだろう。キューブリックよりも6年早い1965年に映画化された本作はワンルーム、わずか2カットであの世界観を完全に再現するという離れ業をやってのけているので個人的にウォーホルの『エンパイア(1964)』、『眠り(1964)』、『チェルシー・ガールズ(1966)』よりも重要だと思っていて、それを本書は優先して掲載している点、信頼できる。
『血ぬられた墓標』あらすじ
18世紀のバルカン地方、魔女とみなされ火炙りの刑に処された王女は一族を呪いながら息絶えた。それから一世紀後、人間の血を吸って礼拝堂の石棺から復活した王女は、自分の曽孫にあたる美しい娘に宿り怨みをはらそうとする……。イタリア怪奇映画の父、M・バーヴァの記念すべき監督第1作。
※Yahoo!映画より引用
マリオ・バーヴァ驚異のデビュー作
モンスター映画ファンの間で神聖化されているマリオ・バーヴァですが、その非凡さはこの監督1作目の緻密さを観れば明らかだろう。マリオ・バーヴァはロベルト・ロッセリーニやラオール・ウォルシュ監督作の撮影で下積みを重ね、制作トラブルを抱えていたリッカルド・フレーダ監督の『吸血鬼(1956)』、『カルティキ/悪魔の人喰い生物(1959)』、ジャック・ターナー『マラソンの戦い(1959)』のピンチヒッターとして監督を代理で取り仕切り、それがきっかけで本作を製作することとなった。
撮影監督出身のマリオ・バーヴァが自らカメラを回して作られた本作は他の怪奇映画とは一線を画するヴィジュアルの圧力で観客の魂を鷲掴みにする。悪魔払いの儀式で、王女は焼印を入れられ、針の仮面を取り付けられる。仮面をハンマーで叩きつけ、瞳から涙が滴る。そこにタイトルが被さる。クールなオープニングから幕を開ける。
学会に急ぐドクター・クルヴァジャンとその弟子アンドレイは、チップを払い薄気味悪い森を駆け抜けることにするのだが、途中で馬車が故障してしまう。そして彼らは好奇心から地下廃墟に足を踏み入れる。この場所が物語の重要拠点になることを示すため、バーヴァは360度パンさせて、空間を説明し、そのまま博士たちの好奇心を象徴するように暗部へググッとフォーカスをあてる。
そしてパニックホラー映画のクリシェのように、「十字架を破壊してはいけない。」というルールを破り、こともあろうことか仮面を外したり、イコンをテイクアウトしたりするのだ。そして、生々しい動きで瞳が再生し、復活した王女が次から次へと村人を血祭りにあげていく。
『妖婆・死棺の呪い』が妖怪VS博士のバトルに特化し、教会の中でのバトルを中心に描いていたのに対し、本作は人をチェスのように動かし、複数の拠点を隠し通路で繋いでいくダイナミックな演出が特徴となっている。そのダイナミックな人の動かしを可能にするために、アンドレイが廃墟のそばを通りかかった美女カーチャに一目惚れする場面では、「さよならなんて言わないよ。またどこかで会おう。」と粋なセリフを言わせていたりする。
そして、物語が中盤に差し掛かると、様々な隠し通路や落とし穴が現れるのだが、どれもそれは漆黒に包まれており、その先にあるものが観客から見えなくなっているため好奇心を刺激するスパイスとして働いている。
マリオ・バーヴァのこだわり故、説明的な描写が多く若干冗長に感じる部分もあれど、『妖婆・死棺の呪い』と甲乙つけがたい傑作でありました。
※画像はIMDbより引用
 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!











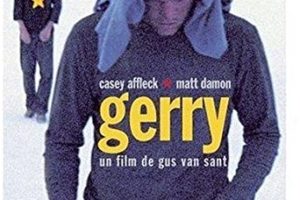











コメントを残す