その手に触れるまで(2019)
原題:Le jeune Ahmed
英題:Young Ahmed
監督:ダルデンヌ兄弟
出演:イディル・ベン・アディ、オリヴィエ・ボノー、ミリエム・アケディウetc
評価:80点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
ベルギーの巨匠にして8作品連続カンヌ国際映画祭コンペティション部門選出の常連ダルデンヌ兄弟がパルムドール、男優賞、女優賞、脚本賞、グランプリに次いで監督賞を受賞し、主要部門全制覇を成し遂げた。しかし、今回監督賞を受賞した『その手に触れるまで』は、賛否両論が監督史上最も割れた問題作と言えよう。イスラム過激派によるテロを扱った作品ながら、84分と非常に短く、また監督の迷いがあり、明確に何故少年が過激派思想にのめり込んだかの過程や過激派思想に取り憑かれた少年をどのように更生させていくのかといった描写が非常に曖昧で明確な答えを示さないが故に賛否が分かれていると言える。
Le Mondeは「ダルデンヌ兄弟に対する共感は、素人俳優を見つけて動かし、偉大な俳優に何が必要なのかを問うところにあります。 イディル・ベン・アディの演技は、緻密でコンパクトな存在感によって映画全体を独占するデモンストレーションとなっています。」と少年役のイディル・ベン・アディから才能を引き出した監督の手腕を賞賛している。
一方で、カイエ・デュ・シネマは「ダルデンヌ兄弟は、彼ら自身を更新することのできぬ無力さで、映画をますます露骨なフォーマットに閉じ込めているようです。すべてが予測可能であります。」と酷評している。FIKMMAKERは今までのダルデンヌ兄弟作品とは違い、カンヌ国際映画祭時に米国公開に向けた販売店を見つけられなかったと語っている(最終的にKino Lorberが配給)。
そんな問題作、日本公開は5/22(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館他にて公開ですが一足早く観賞しました。
『その手に触れるまで』あらすじ
ベルギーに暮らす13歳の少年アーメッド。テレビゲーム好きの普通の少年だった彼は、徐々に尊敬するイマームに感化され、過激なイスラムの思想にのめり込み、考えを認められない先生を殺さねばならない、と思い込んでゆく……。狂信的な考えに憑りつかれてしまった少年の気持ちを変える事はできるのか?
※Filmarksより引用
イスラム過激派のび太くんは何故誕生したのか?
アラビア語のテスト中なのに13歳の少年アメッドは抜け出してしまう。先生の制止を振り払い。熱狂的なイスラム教徒の彼は、サラートの為に会場へ向かっていったのだ。母親は当然起こるのだが、アラビア語で反抗するアメッド。「フランス語で話してよ」とキレる母。軋轢が広がりをみせていく。アメッドは、イスラム過激派だが、彼の眼差しはまるでドラえもんにおけるのび太くんのようにか弱い。暴力的な眼光やオーラを感じないところからつい最近、感化されたことが分かる。そしてその原因が、彼が師匠として尊敬しているイマームだった。イマームはイスラム原理主義者であり、女性に対して嫌悪を抱いている。アメッドのアラビア語教師に平気で暴言を吐く。
そして、コーランの第二章193「迫害がなくなって、この教義がアッラーのため(最も有力なもの)になるまでかれらに対して戦え。」という教えに取り憑かれ、アラビア語教師を殺害しようとするのだ。しかし、彼は熱狂的なイスラム教徒でありながら、ファッションの域を出ていない。故に、コーラン研究でのディスカッションで標的から質問を振られると逃げ出してしまう弱さがあるのだ。これは幼少期にある、閉塞的な社会や大人に対して暴力で克服できるある種の破壊願望を投影した映画のように見える。理由は?と聞かれても、イスラム教徒の父と結婚する為に改宗した母のにわかイスラム教徒っぷりに対する嫌悪以上に、親や先生といった権力者に対する思春期独自の反抗とそこに存在するイマームというカリスマが悪魔合体したものといえる。大人になり大海へ出ると分かる、世界はあまりに大きく理不尽な他者、社会を知らない思春期特有のイキりにフォーカスがあたっているのだ。だから、観客が想像していた貧困や過程環境によりモンスターが生まれたという描写はない。実際に、監督もそういった安易なキャラクター作りを避ける為、アラビア語教師も白人にして本作に望んでいる。
後半は、前半の感情的で激しい描写は落ち着きを魅せ、いかにして彼を更生させていくのかに着目されていく。これこそが監督が描きたいポイントだとしている。信仰の自由を尊重し、彼の尊厳を傷つけないように、農業に従事させることで彼を更生させようとするのです。しかし、なかなか彼の心の奥まで変えることができない。監督は、ひょっとすると映画の中で更生させること自体が欺瞞に満ち溢れ、信仰の自由を奪っているのではと悩んでいるのだろうか。映画は、明確な解決策を提示せずふわふわと浮遊し、いつものダルデンヌ映画的寸止めで映画が終了する。
なるほど、観客の期待した内容を全く魅せない本作は確かに批判の的に晒される作品だ。結局のところ、なんで彼のような人物が生まれたのかは提示されないし、解決策も浅い。しかしながら、この映画はクリシェとして描かれるイスラム過激派の否定、そして思春期の暴力の爆発というものがどういうものかを提示し、観客へ問題を提起しているのだ。
最近のダルデンヌ兄弟映画は、守りに入っていて、尚且つケン・ローチとは違い題材も弱かったりするのだが、この作品は非常に心に残る作品であった。
 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新




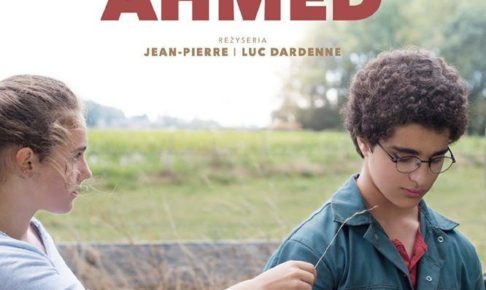






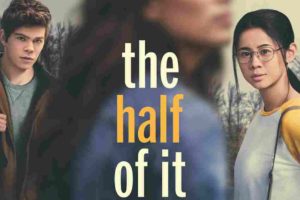

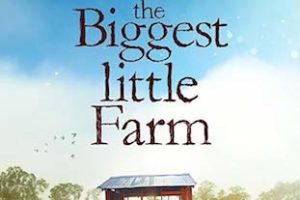








コメントを残す