ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト※旧邦題:ウエスタン(1968)
原題:C’ERA UNA VOLTA IL WEST
英題:Once Upon a Time in the West
監督:セルジオ・レオーネ
出演:チャールズ・ブロンソン、クラウディア・カルディナーレ、ヘンリー・フォンダ、ジェイソン・ロバーズetc
もくじ
評価:5億点
『死ぬまでに観たい映画1001本』に掲載されているセルジオ・レオーネ渾身のマカロニ・ウエスタン『ウエスタン』がこの度、邦題を『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』に改め公開された。
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』あらすじ
マカロニ・ウエスタンで知られるイタリアの巨匠セルジオ・レオーネが1968年に手がけた作品で、日本では当時「ウエスタン」の邦題で短縮版が公開された一作。「荒野の用心棒」(64)、「夕陽のガンマン」(65)、「続・夕陽のガンマン 地獄の決斗」(66)で3年連続イタリア年間興行収入ナンバーワンを記録したレオーネが、方向性を大きく変え、自らの作家性を強く打ち出した野心作。大陸横断鉄道の敷設により新たな文明の波が押し寄せていた西部開拓期を舞台に、女性主人公の目を通して、移り変わる時代とともに滅びゆくガンマンたちの落日を描いた。ニューオーリンズから西部に嫁いできた元高級娼婦のジルは、何者かに家族全員を殺され、広大な荒地の相続人となる。そして、莫大な価値を秘めたその土地の利権をめぐり、殺し屋や強盗団、謎のガンマンらが繰り広げる争いに巻き込まれていく。初公開当時、ヨーロッパでは高い評価を得たが、アメリカでは理解されずにオリジナル版から20分短縮されて興行的にも惨敗。日本ではアメリカ版からさらにカットされた2時間21分の短縮版が「ウエスタン」の邦題で公開された。初公開から50年を経た、レオーネ生誕90年・没後30年にもあたる2019年、原題の英訳「Once Upon a Time in the West」をそのまま訳した「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト」に邦題をあらため、2時間45分のオリジナル版が劇場初公開される。
※映画.comより引用
豊穣な《時間の荒野》に行かないか?
パソコンの登場、スマホの登場で人々の心に余裕が出ると思われていた20世紀は裏切られた。21世紀を生きる我々は、常にテクノロジーの渦に飲み込まれ四六時中動き続けている。今やスマホ一つで仕事ができるので、休日も休まることはない。その影響は映画という娯楽にまで波及した。
そんな今が、パソコンもスマホもない時代の豊穣潤沢に使われる《時間》を目の当たりにすると、とてつもないショックを受ける。と同時に、優雅な映画の旅という至福に涙をするだろう。なんて、芳醇なんだと。
無から《人間味》が滲み出す。そう悪党だって人間なのさ!
さて、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』は20分近い時間を掛けてオープニングを描く贅沢さの大波から始まる。3人のならず者が駅にやってくる。駅員は怯える。恐怖に言葉は要らない。ギョロッと睨む男は、駅員が「7ドル…50セントです…」と手渡す切符を、パラっと風に託し葬り去る。この駅は、悲鳴なくとも支配された。
列車は遅れているらしい。4時間も来ないらしい。
ならず者たちは、360度地平線しかない虚無で標的を待つのだ。その長い長い時間に、恐怖のモザイクに包まれていた彼らの人間味というものが滲み出てくる。一人は、指をポキポキ鳴らす。もう一人は顎に止まる蝿を、吐息で倒そうとする。手で払ったら、漢じゃない。でも痒いし鬱陶しい、その男のプライドを掛けた小さな小さなバトルをじっくりと魅せながら。男が来るのを待つのです。
そして、時は来た。列車がガタンゴトン、ガタンゴトンとやって来る。ならず者は構える。扉が開く、でも駅員が荷物を置くだけ。ひょっとしたら乗っていない?無念、今回は出会えず!じゃあ帰ろう…とした時、立ち去る列車の影からチャールズ・ブロンソン演じる標的が現れるのだ。
彼はハーモニカを取り出し、吹き始める。こんなにも緊迫した状態なのに。その音色は、まるで少年がうぁーんと泣きじゃくるような慟哭である。その音色の重みは、全く部外者であるスクリーンの外側、我々の心をも鷲掴みにします。
そして、ハーモニカの音色が消えた時、火蓋が切られる。そう『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』の始まり始まりだと。
今や、素性不明と言ってもインターネットで検索すれば、輪郭ぐらいはわかってしまうもの。しかし、そんなのが存在しない時代。悪党であっても、その標的の得体の知れなさに微かな恐怖を抱く。そして、来るか来ないか分からない運命をただ、待つことでしか掴めないというのをセルジオ・レオーネは《間》で表現して魅せた。それは『荒野の用心棒』、『夕陽のガンマン』、『続・夕陽のガンマン』と時間表現を磨いてきたセルジオ・レオーネの集大成を感じさせる。
そして彼は、修羅の国に余計なセリフは要らないと、会話をなるべく数秒で、数単語で終わらせようとする。敵を怯えさせるのにベラベラ喋らない。ただ、殺そうとする相手に「Try this(試せよ)」というだけで十分だ。
クラウディア・カルディナーレ演じる夫人の元に来るはずの家族が来ない描写も、8時50分の駅時計と10時10分を示す自前の時計をカットで繋ぐだけで表現可能だ。
今の映画にありがちな、説明しないように魅せているがベラベラ饒舌理詰めで説明するようなことはしないのです。
そして、時間をじっくり掛けてアクションは圧倒的手数と、登場人物誰しもが抱く恐怖を滲ませトリガーをなかなか引かせない間でもって観客をスクリーン内部へと引き摺り込む。
西部開拓時代の空気=野生性
本作は、悪党にだって安全が保証されていない修羅の国だった頃のアメリカの人々をアーカイブすることに成功している。その中で、最も素晴らしいのは《野生の勘》をアーカイブしたというところにある。
片田舎の町の一家団欒の場面。母と息子、父が和気藹々と食事の準備をしている。荒野のザザッと砂が舞う音が響き渡っているのだが、突然それが止まる。すると、母と父が何かを感じ取ったように静止し、ジーーーーーッと周りを見渡す。束の間の無、それが再び動き始めると、何事もなかったかのように団欒は再開される。しかし、また何か気配を感じ、ジッと止まると、銃がバーーーン!バーーーン!と鳴り始め、隠れていた悪党が姿を表す。そして、女、子供だろうと情け無用で殺す。そうです、修羅の国では、情で殺しを躊躇すると自分の命が危ないのです。
まるで、草むらの陰から野生動物を狙うライオンの狩りを観ているような臨場感溢れる空間は、空気を捉えることでより一層リアリズムを増幅させるのです。
列車でのバトルシーンに注目
西部劇、特にマカロニ・ウエスタンというと、銃をとにかくバンバン撃つイメージが強い。銃を撃つというのは至近距離で人が死ぬのを目の当たりにすること。銃を撃つことで自分が死ぬ可能性が一気に上がるということ。実際には、そんなにバンバン撃てません。なので、本作での銃撃戦はじっくりと間を持たせる。そしてアイデアで持ってなんとか敵を倒そうとする。例えば、シャイアン(ジェイソン・ロバーズ)が黒幕モートンを追い列車に侵入する場面。じっくりと角度を見定め、窓の外から、手下を撃つ。跳弾で椅子を回転させ、反撃させないようにする。
屋根の上を歩くと、ギシギシ音が鳴る。自分の立ち位置は相手にわかってしまう。だから、靴を車窓から見えるように降ろし、敵を油断させたところで、靴の中に仕込んだ銃で、敵の目玉を吹き飛ばすのです。
そして松葉杖ヨロヨロなモートン一人になったところで、にじり寄り揺さぶる。戦略的に人を殺めているその美学に感動しない人はいないでしょう。
また、その一部始終をニヤリと笑いながら見守るハーモニカ(チャールズ・ブロンソン)。そしてドヤ顔で車内に入るシャイアンに対して、「銃しかないのかい?」と煽りながら助けを求める粋なスカしっぷりにさらなる興奮を覚えます。
主観と客観の戦闘
終盤の町の中での銃撃戦は、ハーモニカによる岡目八目客観の視点が、フランク(ヘンリー・フォンダ)の主観を助け、
客観→主観
主観→主観
客観→主観→主観
といった立体感と臨場感を120%引き出したアクションを紡ぎだし、盛り上がりを魅せる。
ハーモニカはクラウディア・カルディナーレ演じるジル・マクベインが入浴中だというのに、ばっ!とバスルームに入る。キャッ!と乳房を隠す彼女に対して、サッとアイテムを渡し、窓を覗き込む。外の風景が映るが、敵がどこにいるのか分からない。しかし、二人は分かっているようだ。そして眼下ではシャイアンが歩いている。敵を仕留める為に。ただフランクの《主観》な瞳からはその敵は見えない。それをハーモニカが助けるのです。彼がズドン!と弾を打ち込むと、布が破れ、敵が落ちてくるのだ。ここから二人は連係プレイで刺客を血祭りに上げていく。12時の方さとハーモニカが言うと、シャイアンは時計台にいる敵を倒す。あれだけ、食えない男たちだったのが、ここにきて運命共同体、以心伝心で敵をやっつけていくのです。呉越同舟とはひょっとしたらこういうことを言うのかもしれません。
昔々、西部の田舎町で…
そしてハーモニカ、後ろ盾を失った黒幕Mr.ChooChoo汽車のダンナことモートン、そして一家を殺されたマクベイン姉貴に彼女の周りをまとわりつくフランクがそれぞれの人生の終着点に向かって、それぞれの物語が一つに収斂していく。
ハーモニカはシャイアンと遂に決闘をする。そこで長い長い回想が蘇り、ハーモニカの音色が紡ぐ少年の慟哭は、かつて彼が悪党にハーモニカを咥えさせられながら親を殺されたあの苦しみが染み込んでいることを強調する。そして決闘に勝利した彼は、フランクと共に去ろうとするのだが、フランクは自分の命がもうないことを悟りこの地に残ることを決意する。そこには、西部開拓時代の終わり、新たな時代に踏み出すことを拒絶する男のプライドが光るのだ。
味方を失ったモートンは、最後の賭けを行う。しかし、観客にはそのプロセスは魅せず、その結果が映し出される。列車は止まり、外で地を這うように蠢くモートンがそこにいました。
マクベインは、鉄道ができるであろう土地に新たな人生のページを綴ろうとする。
こうして幾重にも重なった人生はそれぞれの終着駅で光り輝いて終わる。その美しさに涙しました。
最後に…
西部劇やマカロニ・ウエスタンは午後のロードショーやレンタルで勉強的に観ており、通俗な映画として斜めに構えていました。しかし、本作を新宿ピカデリーの大スクリーンで観て気づきました。
《私は西部劇なんて観てなかった》
善悪を超越し、それぞれが今を生きようとする。それが西部の、アメリカの歴史を紡ぐそのロマンと野生の生活を生き抜く時に身につけた凄技ガンテクニックのカッコ良さ、これを大スクリーンで観る多幸感は計り知れない。こんな絶景を魅せられた人は、西部劇にハマるだろう。そしてただただ銃をバンバン撃つだけの西部劇に口うるさくなってしまうのもよく分かる。
と言うわけで今年暫定1位の特大ホームランにブンブン一本満足でした。
 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

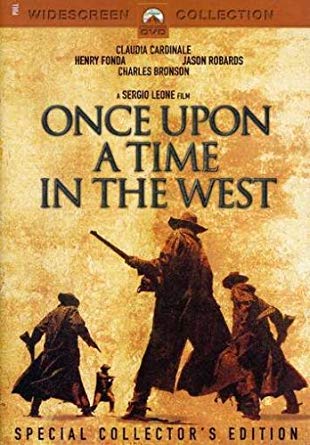




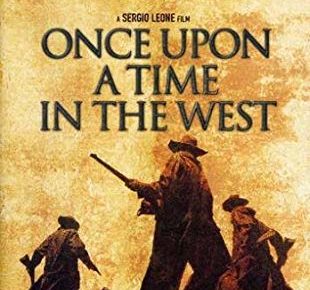

















列車のシーンのところからフランクとシャイアンが逆になってませんか?
なかゆーさん、ありがとうございます!確かに逆になってました!修正しました。