ピッチ上の女たち(2018)
COMME DES GARÇONS

監督:ジュリアン・アラール
出演:マックス・ブービル,ヴァネッサ・ギドetc
評価:60点
こんにちは、チェ・ブンブンです。
青山シアターで開催中のマイフレンチフィルムフェスティバル2本目は、フランス女子サッカー誕生までの過程を描いた実話モノ『ピッチ上の女たち』を鑑賞しました。銀座界隈で上映されてそうなマダム感満載なおしゃれフレンチながら、ジェンダー問題に切り込んだなかなか鋭い作品でした。
『ピッチ上の女たち』あらすじ
1969年フランスの「ル・シャンプノワ」編集社。スポーツ紙面を盛上げるべく、ポールは女子サッカーの試合を企画する。とは言っても、ポールは女子とイチャつきたいだけ。しかし、そんな企画が、フランス女子サッカーを誕生させるきっかけになった!フランス語の中のジェンダー論
本作は、女子サッカーを誕生させ、「サッカーは男のもの」というイメージを変えた実話を描いた話だ。そう聞くと、真面目な社会派ドラマに見えるのだが、本作は全く違うアプローチで描いている。というのも、サッカー熱のある女子が全力で女性としての立場を声高らかに叫ぶわけでもなく、キャッキャ遊んでいたら、いつの間にかサッカー史に新たな1ページを作ってしまったよというノリなのだ。男との試合も、まるで体育の授業のような感じで真剣さがありません。そしてこの手のスポーツ映画にありがちなガチの試合はテロップで終わらせてしまう。なので、実話モノならではの胸熱ドラマを求めて観ると肩透かしを食らう。
しかしながら、#MeToo運動等で、フェミニズムが強烈なものとなり、映画の中でもポリコレによって綺麗でお行儀のいい映画が多くなっている今、1960年代後半の、無自覚な女性蔑視を赤裸々に描いていることは非常に意味があります。特にフランス語を少し知っていると、フランス語がいかに無自覚な女性蔑視をしてしまっているのかがよく分かります。というのも、フランス語には男性名詞と女性名詞があり、女性っぽいものには、女性的な語尾がつけられます。そして、「夫」という単語は存在するのに、「妻」という単語は存在せず、「私の妻」という時に、「Ma femme(=俺の女)」という言い方をしないといけなかったりします。
そんな中、この作品で面白かったのは、日本字幕では「女子サッカー」と一括りにされていたのですが、よく聞くと言葉を使い分けていたところにあります。
チャラ男のポールは「女子サッカー」を”footballeur(サッカー選手)”という言葉に女性形語尾をつけて”footballeurse”と呼んでいた。一方、他の人は”Le foot de fille(女のサッカー)”と呼んでいた。日本的に言えば、ポールは《サカジョ》と呼び、他の人は《女子サッカー》と呼んでいる違いがあります。実は、この映画女たらしでゲス野郎のポールの方が、実は男女の垣根をあっさりと取り払っていたことを暴いた作品だったのです。他のジャーナリストは、サッカーを男のものだと思い込んでいて、それで「女子」という区別の言葉をつけようとする。それに対して、ポールは最初から、「女性」という壁を低くし、それを壊していくことで世の中のジェンダーに対する見方を変えていったと考えることができます。
これを観ると、ブンブンも結構ブログ記事で無意識に「女性監督が」といった書き方をすることがあるので、ジェンダーに対する無自覚な線引きにもっと目を配らねばいけないなと思ってしまいます。この作品で描かれる無意識の女性蔑視にストレス溜まる人もいるかもしれない。しかし、それは監督の狙いです。是非挑戦してみてください。



 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新



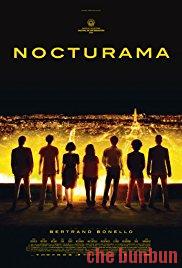













コメントを残す