華氏451(2018)
Fahrenheit 451

監督:ラミン・バーラニ
出演:マイケル・B・ジョーダン、ソフィア・ブテラ、マイケル・シャノンetc
もくじ
評価:25点
何故か東京フィルメックスで、フィルメックスらしくない映画が上映された。その名も『華氏451』。レイ・ブラッドベリの同名小説の映画化で、かつてヌーヴェルヴァーグの巨匠フランソワ・トリュフォーの手によって映画化されたことで有名な物語だ。予告編を観ると、コテコテのアメリカSF映画だ。なんでフィルメックスで上映されたのだろうと思ったら、脚本にイランの名匠アミール・ナデリが参画していたからなのだそう。それにしてもIMDbでの評価は★4.9と低い。かつて、映画評論家の高橋ヨシキはアメリカ人が映画化すると凄い雑な話になるであろうと語っていた。どうも今回の映画版はその様だ。一抹の不安を抱きながら観て観ました…
※レイ・ブラッドベリ版及び、フランソワ・トリュフォー版の結末にも触れているネタバレ記事です
『華氏451』あらすじ
時は近未来。本は有害とされ、消防士の手によって焼かれていた。消防士のガイ・モンタグは、優秀な消防士。上司のビーティの下でエリート街道を進んでいた。そんなある日、若い女性に出会う。そして、婆さんの焼身自殺を見てしまってから、社会制度に疑問を持ち始め、ついに家宅捜査現場から本を盗み出してしまう…2018年だからこその面白さがあった筈なのに…
『華氏451』ほど今リメイクするにもってこいの作品はなかろう。なんたってフランソワ・トリュフォーが映画化した1966年には、スマホはなかった。それどころか家庭用PCすらなかったのだ。レイ・ブラッドベリが本作を書いた時代、及びトリュフォーの時代は、本を焼いたら終わり。モノでアーカイブすることができないからこそ、一人一冊本を暗記することで継承した。ジョージ・オーウェルの『1984年』とほとんど同じプロットの物語だが、オーウェルと違うところは、皮肉のキレにある。火を消す存在である消防士が、自ら火を放つアベコベさはもちろん、ブラッドベリ本作における最大の成功は、未来の話なのに文化が古代ギリシア時代の口承文学の頃まで逆行してしまう荒唐無稽な世界を創り出したことにある。
それを、2010年代。ブラッドベリが想像していたであろう時代に映画化するとは面白い試みだ。なんたって、今はパソコンがある。いやパソコンよりも人々はスマホという板チョコよりも小さい板状のものを通じて世界中の情報にアクセスできる。出版物は売れなくなってきているし、電子書籍もそこまで普及しているとは言えない。しかしながら、人々はSNSやブログ、そして短い記事を毎日浴びるように読んでいる時代。情報は、ネットやクラウド上に漂っているのだ。そんな時代でも口承文学オチは十分通用するのだが、そのプロセスにいかにしてこの現代の様子を投影させていくのかが気になった。
しかし、蓋を開けてみれば、実に中途半端な映画化であった。
そこで3つのポイントに絞って語ります。
1.比喩が通じない皮肉が伝わりにくい
この映画化の最大のグッドポイントは上司役にマイケル・シャノン、部下役にマイケル・B・ジョーダンを起用したことだろう。シャノン扮する上司は徹底して本を焼き払う美学をジョーダン扮する部下に叩き込む。しかしながら、説明が常に文学的なので毎回部下が「えっ?なんて?」と聞き返すのだ。シャノンのムッツリ顔が見事にマッチしている。恐らく、上司はとても本が好きなんだろう。本は沢山の知識を与えるが、その魅力を格下に教えてしまったら、格下がメキメキと知識という武器を備え、自分の地位が危うくなってしまう。だから、徹底的に本を抑圧する。そして、自分だけしか知らない言葉で語ることで自分を大きく見せようとする。まさしく、言論統制で人々から言葉の杖を奪い、その杖でもって統治する本作の世界観を象徴する人物として上司というキャラクターは肉付けされている。そう考えた時に、マイケル・シャノンのムッツリ顔はとてつもなく魅力的に感じる。そして、『クリード チャンプを継ぐ男
』の主人公アドニス・クリードのイメージが記憶に新しいマイケル・B・ジョーダンを起用することで、知識面でにマウントされている状態から立ち上がる様に熱いドラマが生まれやすくなる。
実に魅力的なキャスティングであるにも関わらず、肝心な比喩が通じない皮肉描写というのがすこぶる弱く感じた。ドストエフスキーの『地下室の手記』にハマる前のガイ・モンタグとハマった後、上司にバレないようにこそこそとするモンタグの心情は異なるはずだ。故に、上官の比喩に対する反応も変化するはずなのだが、それが見えにくい。特に、終盤、上司がモンタグに火がついた『罪と罰』を読ませる場面。狼狽するのか、ポーカーフェイスを貫くのかが中途半端。明らかに上司にはバレバレなんだけれども、なんとかしてバレないように装う様子を真面目に、重厚に撮り過ぎている為、最大の盛り上がりが台無しになっているような気がした。
2.クラウド描写があまりに弱い
さて、これが一番問題なところと言える。本作では本の情報をデータアーカイブし、インターネットを通じて世界中に伝播させようとする場面がある。ブラッドベリやトリュフォーの時代には想像できない現代ならではの場面だ。しかし、ここに対する掘り下げがあまりにも弱い。本をデータとして転送しているサーバーを物理的に破壊する場面はあるが、ネットにあがってしまった本を削除したり統制する場面や、そのシステムについて言及する場面はない。また、活字は毒だと言っている割にスクリーンには文字が映っていたりする。クラウドにアップされてしまった本や、そもそもネットに書かれる情報についての弾圧を明確に描いてこそ本作のリメイクとしての価値はあるのに、表面をなぞっただけのシーンが続きます。
3.暗記族との邂逅のその先を描いているはずが…
この描写が原因となって、暗記族の場面が弱いものとなってしまう。クラウドにアップしても本は弾圧されてしまう。ならば、暗記だと口承文学の時代に逆行する。今回のアップグレード版は、このプロセスが重要となっているのだが、そこが甘い。本作は暗記族との邂逅を時間かけて掘り下げようとしているのだが、暗記族がただのチェスの駒のように動き、軽々しく消防士に駆逐されていく。そして、暗記族を捨て駒のように使い、モンタグの英雄譚へと押し上げ映画は終わってしまう。皮肉なのか、ウイルスのように本の情報を鳥に取り付け外に放ち映画は終わるのだが、ブラッドベリの口承文学オチと比べると非常にキレが悪い。カタルシスも感じにくかったりする。
最後に…
マイケル・シャノンのムッツリ顔は面白かった。俗にエクストリームエロ本隠し譚と呼ばれているこの物語にふさわしい配役だった。しかしながら、ブラッドベリ版とトリュフォー版が好きなブンブンにはなかなか厳しいものがある作品でした。高橋ヨシキさんの未来予想通りの映画でがっかりでした。






 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!



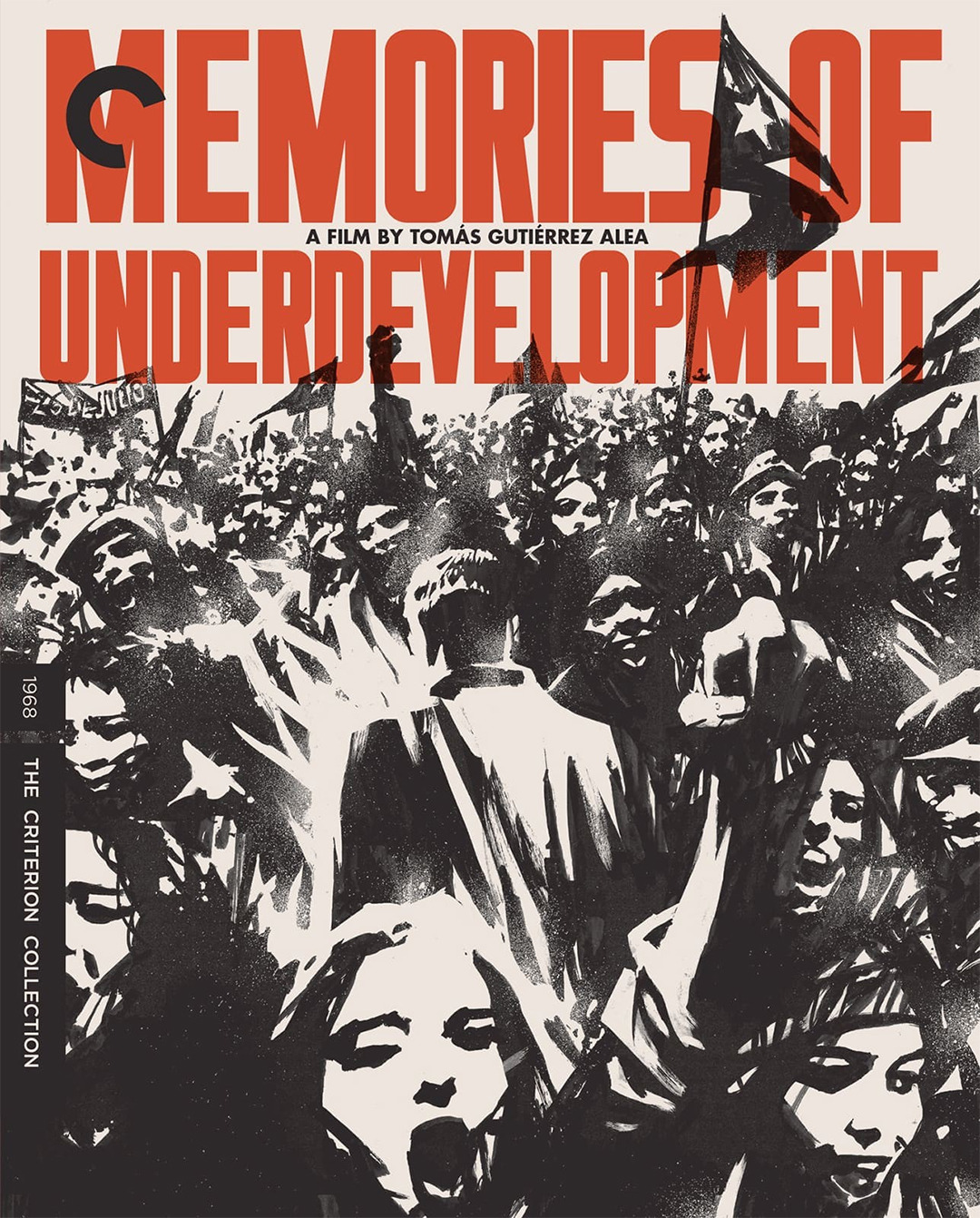



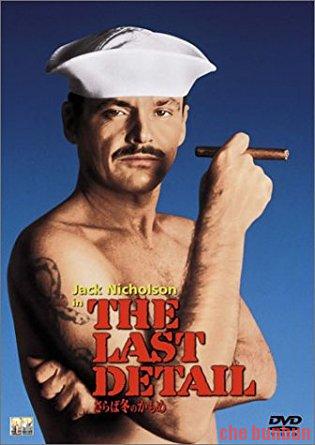








コメントを残す