『ボヘミアン・ラプソディ』あらすじ
Queenのヴォーカル、フレディ・マーキュリーの変遷を追ったドラマ。インドからイギリスに渡った一家の息子ファルーク・バルサラは、フレディと名乗り、ライブハウスに出入りしていた。そして、やがて彼は仲間を見つけ、Queenを結成する。破天荒な音楽作りで、有名になっていくバンド。しかしながら、フレディの中に眠るコンプレックスが、メンバー内で対立を引き起こし、やがてバンドは分裂してしまう。そんな彼らは、何故ライブエイドで復活を遂げたのだろうか?『ソーシャル・ネットワーク』的現代の『華麗なるギャツビー』
本作は、事実とかなり異なることで批判されている。バンド決裂の危機として、フレディのソロ・アルバム発売のエピソードがあるが、実際にはロジャーとブライアンが先に出している。また、ライブエイドでもってメンバーが和解する場面で、「もう何年も演奏していない」というセリフがあるが、The Works Tourでブラジル・リオデジャネイロや南アフリカのサンシティでライブをしている。ただ、事実と違うというところで批判するのはどうなのだろうか?
よくある問題として《Based on a true story問題》がある。映画の始まりに、Based on a true story(事実に基づく映画です)と表記することに対し、「映画は必ず脚色があるのでわざわざ書く必要はない。寧ろ、事実なんだから多少の粗は許せという免罪符に見える」という批判がある。Based on a true storyと書く映画に悪い作品は滅多にないとは思っているものの、やはり事実を映画としていかに翻訳するのかが《映画》の仕事であるので、わざわざ書く必要はないと思っている。
そして、この映画はアーティストの映画だ。戦争ドラマとは違うし、事実の正確さを求められるドキュメンタリーとも違う。エンターテイメントに吹っ切れていていいじゃないか!そもそもQueenは多くの逸話があり、それを全て映画に入れることは不可能だ。人生は映画とは違って綺麗に整っている訳ではない。フレディの生き様に焦点を絞っているのだから、一人の男の物語として描くべきだと思っている。なので、海外批評家の切り口はあまり賛同できない。
それでも、本作はかなり歪であった。物語的問題に満ちた作品だ。というのも、この映画はラスト20分で、ライブエイドを完全再現する為に物語が動いている為、重要な部分が駆け足で進んでいるのだ。例えば、フレディはインドの家系出身というエピソード。家族からは「なんで自分をフレディだと言うの?ファルーク・バルサラでしょ?」と言われるが、しきりにフレディという名前を使う。Queenのメンバーを家族に紹介する場面で、フレディの過去が明らかにされるのだが、フレディは聞きたくないかのように歌い始める。何故、フレディは国籍も名前も変えたのか?それは街中でパキスタン野郎と差別されるから、出っ歯を中傷されるから。一応劇中で原因らしきイベントは発生するのだが、結局その理由は明らかにされない。そして、いかにも重要そうな前半のコンプレックス描写について処理せず、いつの間にかバイセクシャルの問題にすり替えてしまっている。
また、Queenのメンバーとの出会いはあっさりとしている。出会った次の瞬間にはバンドが結成されており、次のシーンでは変わり者であるフレディの言いなりにメンバーがなっているのだ。バンドが成長していくプロセスはほとんど描かれず、いきなり成熟したバンドのように見えてしまうのだ。
本作の前半部分に、批評家が手を叩いて酷評したくなるポイントが多く、また割と中盤退屈する場面も多く、何と言ってもQueenの名曲でゴリ押ししているのが見え見えな物語運びとなっている。これは、確かにキツイものがある。
物語序盤、フレディは家族に対して「過去なんてどうでもいい。俺は未来しか見ないから」という。そして、底抜けに明るく振る舞い、Don’t stop me nowといわんばかりのイケイケドンドンさで前へ前へと進んでいく。しかしながら、彼は一人になると、悲しさを顔に浮かべながら歌詞を綴り出す。メンバーにも打ち明けていない、差別に対する苦しさ、そしてメアリー・オースティンを愛するもののポール・プレンターとも付き合っているバイセクシャルとしての葛藤が歌詞に暗号のようにして吐露されていく。
そしてコントロールできない感情が、メアリーとの破局、そしてメンバーとの仲違いを生んでしまう。フレディは独りいきがって曲を作るのだが、傑作が生まれず苦悩する。そこに、自身がAIDSで死にゆく運命にあるという知らせを突きつけられ、死の淵に立たされた彼はようやく過去と、そして自分と対峙する。
そして
Ooh somebody, ooh somebody
Can anybody find me somebody to love?
と失われた愛を渇望し、這うようにして自ら捨てた仲間の元へ向かう。これがライブエイドのWe are the championsに繋がってくる。Weとは、もちろん完全解散を免れたQueenのことでもあるが、フレディそしてファルーク双方のアイデンティティにとってもチャンピオンだということを物語っているのだ。
このように考えた際に、前半の物語の粗さは正当化することができる。つまりは、傲慢で自己中心的だったフレディ目線の話なのだ。だからコンプレックスと向き合わない、無視しようとする描写は必然と言える。また、独裁者的存在なので、メンバーがフレディの意のままに動く、アイデアを出してくれるというのも合点がいくのだ。そしてタイトルが『どんと・ストップ・ミー・ナウ』とか『ウィ・ウィル・ロック・ユー』ではなく『ボヘミアン・ラプソディ』なのも納得がいく。これは紛れもないロックオペラなのだ。
ライブエイドの完全再現
ただ、それだけならブンブンも批評家同様酷評になっていたであろう。なんたって、いくら技術的に高度であっても、あまりに中盤退屈なのだから。バイセクシャルとして苦しむフレディ像のセクションが、ファスビンダー映画のようにねっとりとしており、体感時間が異様に長く感じる。エンタメ音楽映画でファスビンダーはいいですよと思いたくなる。
Queenもここで25分に渡りパフォーマンスをする。セットリストは、
1.ボヘミアン・ラプソディ(Bohemian Rhapsody)
2.レディオ・ガガ(Radio gaga)
3.ハマー・トゥ・フォール(Hammer to Fall)
4.クレイジー・リトル・シング・コールド・ラヴ(Crazy Little Thing Called Love)
5.ウィ・ウィル・ロック・ユー(We Will Rock You)
6.ウィ・アー・ザ・チャンピオン(We Are the Champions)
だ。
なんとこの作品、このライブエイドのパフォーマンスを映画の中で魅せてくれるのだ。もちろん、映画なので、それも劇映画なので、泣く泣くウィ・ウィル・ロック・ユー(We Will Rock You)なんかは削られているの(これは英断だと思う。これをやってしまったら、『ボヘミアン・ラプソディ』というタイトルが弱まってしまうし、中盤で一度やっているので、クドイ演出になってしまう)だが、フレディのパフォーマンスや、ピアノの上に置かれたビール、客席から掲げられる横断幕まで完璧に再現されているのだ。観客は、2時間近くフレディの生き様を見てきた。そして、彼がまだ観客やメディアには秘密にしていたAIDSのことも知っている。だからこそ、フレディが最期の力を振り絞って歌い狂い、最後の最後にWe are the championsと叫ぶ。客席からもWe are the championsと木霊が返ってくる場面に涙してしまうのだ。
そして後悔する。なんで俺は普通の上映会に来てしまったのだろう。こんなにも、立つこともできず、絶叫もできず、歌うことも許されない空間でフレディの叫びを聴くのが辛いとは!確かにこの2時間退屈だったところもあるし、作劇として上手いとは言えない部分も多かった。でもね、でもね、このライブエイドがそんなことどうでもいいじゃんと教えてくれる。事実とは違うけど、そこには人間が描かれていた。一人の人間、いや一つのバンドの熱い物語があった。何よりも、我々が当たり前のように耳にするQueenの曲の魅力に再度気づかせてくれた。こんなに素晴らしい映画を貶すことなんてブンブンにはできない。そして、職場の人や周りの映画好きに、「今、オススメの映画何か知っている?」と訊かれたら有無を言わさずこう答えるであろう。
「『ボヘミアン・ラプソディ』だ。何も言うな。とにかく観てくれ!」と。
映画祭シーズン、予算と時間が足りずなかなか一般公開の作品に手が回らないブンブンですが、これは観て良かった。素晴らしい映画体験であったことは間違いない。そして、絶叫上映、応援上映で観なかったことを悔やみました。






 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!



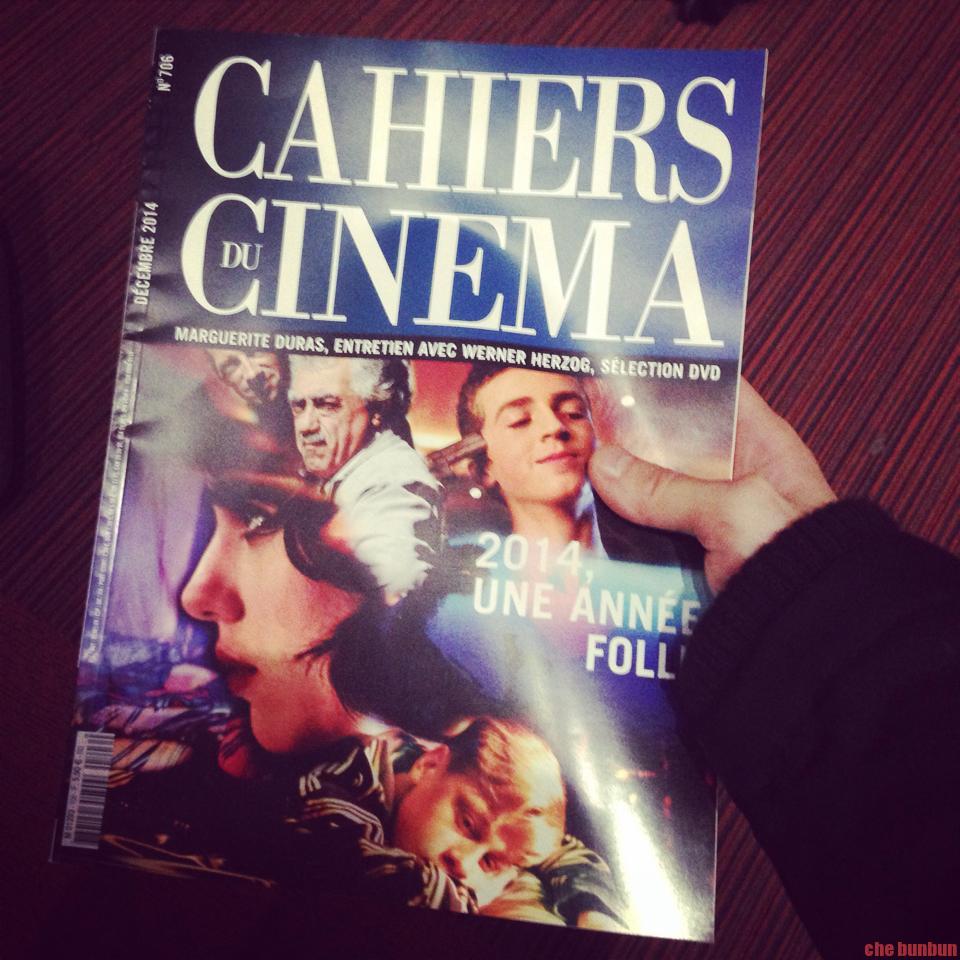
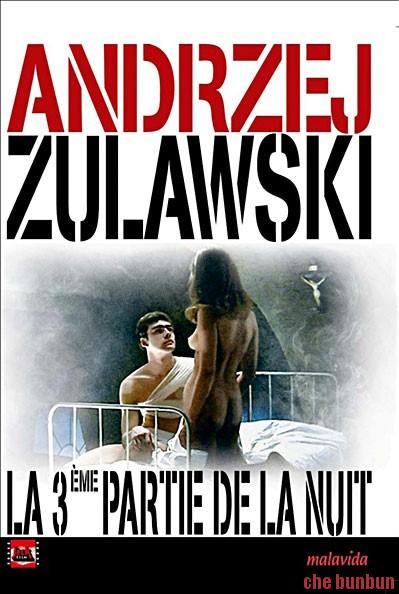
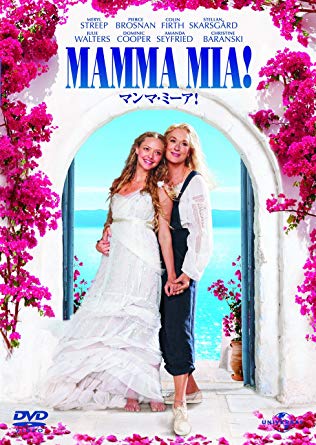
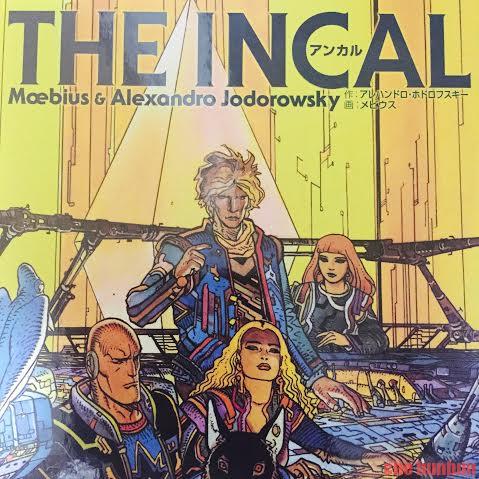









コメントを残す