悪魔の季節(2018)
原題:Ang panahon ng halimaw
英題:Season of the Devil

監督:ラヴ・ディアス
出演:ピオロ・パスカル、シャイーナ・マグダヤオ、ピンキー・アマドアetc
もくじ
評価:80点
東京国際映画祭個人的最大の目玉はラヴ・ディアス監督の『悪魔の季節』だった。ラヴ・ディアスは、上映時間が平気で3時間を超え、寧ろ4時間未満だと「短い」と錯覚する鬼才だ。こともあろうことか、そんな超大作を1年に1本ペースで作るので、ハードコアシネフィルにとって涙モノの監督である。日本でも昨年、『立ち去った女』が奇跡の公開を果たし、ラヴ・ディアスの知名度が高まった。そんな中、今回4時間弱のロックオペラが完成し、東京国際映画祭で上映された。
』に関してはオールタイムベスト1位に挙げている程好きな監督。果たして今回はどうだったのか?しっかりメモを取りながら観たので細かくまとめていきます。尚、ネタバレ記事なので、ご注意ください。
『悪魔の季節』あらすじ
1979年フィリピン南部で起きた虐殺事件に基づくロックオペラ。詩人のフーゴ・ハニウェイは、戒厳令により兵士が村を横暴な態度で支配するフィリピン社会を批判し、マルコス政権に対する怒りを詩に籠めていた。そんな中、妻のロリーナは医者としてフィリピン南部のギント村に診療所を開くといい夫の制止を振り切って去ってしまう。フーゴは精神が病んでしまい、酒に溺れるようになる。一方、妻は執拗な軍の嫌がらせに悩まされる。そしてある日、ロリーナからの手紙が途絶えた。フーゴは、意を決してギント村へ潜入することにするのだが…ラヴ・ディアスの怒り
ラヴ・ディアス監督作といえば、何気ないフィリピン田舎町の日常を淡々と映し、その中で段々と1970年代フェルディナンド・マルコス大統領が発令した戒厳令時代の息苦しさが見えてくる作風で一貫している監督だ。観る者にあの時代のフィリピンの生活を追体験させることで、フィリピンが持つ独裁支配の歴史を伝えようとしている。しかしながら、今回の『悪魔の季節』では、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の横暴に憤怒したのだろうか?ラヴ・ディアスの怒りが4時間余すことなく炸裂していた。
ロドリゴ・ドゥテルテとは、16歳にして人を刺し殺し
、ダバオ市長時代にはダバオ・デス・スクワッド(Davao Death Squads)という自警団を使って犯罪者を片っ端から抹殺していった。そして現在、大統領にまで登り詰めた彼は、世界中の批判をものとはせず、麻薬撲滅の為に超法規的殺人指令で持って犯罪者を皆殺しにしているのだ。BBCの報告に夜と、昨年、麻薬撲滅作戦から警察を除外し麻薬取締局が中心となって活動するようになった
。現実に君臨する夜神月として猛威を振るっているドゥテルテ大統領に対する怒りがどのように炸裂したかを書いていく。
兵士の描写
ラヴ・ディアス監督作はIMDbによると29本存在している。ブンブンはその中の僅か6本しか観ていないアマチュアなのだが、それでも他のラヴ・ディアス作品とはテイストが全く異なる。それは全編アカペラのミュージカルといった表面的次元に止まることはない。何と言っても《兵士》の描写が180度違う。ラヴ・ディアスには必ずといってもいいほど兵士の横暴が描かれる。しかし、従来の兵士描写は、フィリピン田舎町に兵士が幽霊のようにやってきて、特に説明なく人を殺したり、嫌がらせをする。戒厳令で村にやってきて悪さをするという最低限のフレームで説明し、不条理に現れては消えるを繰り返すのだ。この不条理さが、1970年代、田舎町にまで波及する支配の息苦しさを観客に追体験させる。
ただ、今回は全てセリフで、兵士の立ち位置から役割、どういった存在なのかを説明する。映画において、過度な説明描写はダメダメ映画の烙印を押される典型。ましてや脚本の世界では行間を描くことが美徳とされているのだ。そのタブーを傑作という形で破る為に、《オペラ》という要素を盛り込んだ。オペラにおいては、いかに感情の吐露をドラマチックに描くのかが肝となってくる。後述するが、本作には感情の吐露をドラマチックに描く為に様々な技巧が凝らされており、これにより駄作に陥ることを回避。そして、監督の今まで暗号のように押し殺してきた軍に対する怒りを露骨に描いた。
ギント村の兵士は、村人に対して
俺は兵士だ!
確信が変化をもたらす!
と豪語する。俺たちが村を守っているのだから、村は平和なんだと。だから逆らうなと、銃で村人を脅す。
それに対して村人は、
天国も地球も楽園なんかじゃない
我々人は決して学ばない
我々の人生に確かなものはない
今での幽霊を信じる
ウソがまかり通る
と嘆き、意を決して兵士のアジトに行き、兵士の横暴さを指摘する。《自分が法》のようにならないで、この村を破壊しないでと代表者が言うと、兵士は、
これは合法的仕事だ
法に則った仕事
法律には従うしかない
人も社会も法に従うべき
ナルシソ(村の支配者)もこの村が好きだよ
と綺麗事を言って追い出す。LA LA LA~と軽妙なフレーズからは、綺麗な言葉を言いつつ、横暴冷酷さで村を支配しようとする魂胆が見え隠れし、不気味さが増していく。
このような、従来のラヴ・ディアス映画では観られない、直接的な表現が数多映画に組み込まれている。そして、直接的に描く為に、物語も非常にシンプルになっている。要は『シェルブールの雨傘』における、去った男を待ち焦がれるヒロインのパートにアルジェ戦争でサバイバルしている男のパートを付加した話だ。いつものような、様々な挿話を組み合わせて、4時間以上かけてゆっくり収斂させていく手法を棄てている。
表の顔、裏の顔
そして、ラヴ・ディアスは怒りの表現として、一番これがやりたかったのだろう。村の支配者ナルシソのトゥー・フェイスを映画の中盤に持ってくる。ロリーナが、麻薬の運び屋容疑で兵士に夫を誘拐された女性と一緒にアジトに殴り込みに行き直談判する場面。奥から、村の支配者ナルシソが現れ、演説を始める。そして兵士が
LA LA LA
LA LA LA
LA LA LA aah!
とリズムを刻みながらナルシソの演説を聴けと彼女らに迫る。やがて、ナルシソがカメラに近づき後ろを向く。すると顔の後ろにインテリゲンチャに見える顔がくっついていることに観客が気がつき、ゾッとする。この映画が何度も強調する、「表の顔、裏の顔」、「ウソも何度も刷り込めばそれは真実になる」ということを象徴させている。あまりに露骨で、カメラワークも無理矢理裏の顔を魅せようとしているので、「おいおい、どうしちまったんだラヴ・ディアス。演出としてあまりに下手なのでは?」と思うのだが、それだけドゥテルテ大統領の横暴さに怒りを感じ、映画のクオリティを下げてまで直接的表現を使わざる得なかったラヴ・ディアスの切迫した気持ちが伺える。
ロックオペラが物語にもたらす機能
さて、確信に迫っていくとしよう。本作のロックオペラについて迫ろう。本作は、メロディをクドイぐらいに何度も何度も繰り返す。しかも、別のシーンでその曲をまた登場させてくる。なので、重複なければ90分ぐらいに収まりそうな作品となっている。
例えば、冒頭から次の歌詞が何度も、観客が忘れた頃に木霊する。
世界がメロディを失うなら
どうやって子守唄を歌えば良い?
世界が心を失うなら
どうやって痛みに耐えれば良い?
まさしく、民衆を殺しても簡単に隠せる。歴史を都合よく変えるのを許していいのか?という問題提起を、ウソも何度も言えば本当になってしまうことフィリピン社会が悪用してきた手法に対して、同様の手法でカウンターパンチを食らわせていると言えよう。現に、観終わった後、友人とファミレスで語り合ったのだが、曲が脳裏を離れないと口々に語っていました。そんな中、下記の2つの曲が強烈に脳裏に焼きついた。
執拗なLA LA LAND
本作において最も素晴らしいのは、Twitterでも『ラ・ラ・ランド
』だ!と話題になっているLA LA LAの旋律だ。脳裏に焼くつくほど幾重にも積むように、LA LA LAの旋律が歌われる。しかし、それが毎回意味が違うのだ。
それこそ、兵士が歌うときは、兵士の恐怖を強調する為に対位法として軽快なこの曲が使われる。それによって村人同様に、観客も戦慄する。
兵士にレイプされチョウセンアサガオの覚醒剤入りドリンクを飲まされたロリーナがこの曲を歌う時、それは兵士の服従を示す。
兵士に拷問されている中、フーゴが歌う時、それは兵士に対する怒り、絶対服従せんぞ!妻を返しやがれ!という意味に変わる。
この一つのメロディーに対する多様性が、本作における《本音と建前》に対する深い掘り下げに貢献している。
チョウセンアサガオのブルース(Talampunay Blues)
LA LA LAの旋律と並び、観客の脳裏に焼きつくのは、ロレーナを兵士がレイプする時に、彼らが歌う《チョウセンアサガオのブルース(Talampunay Blues)》。
Nawala ang sakit
Nawala ang galit
Nawala ang kalungkutan
Nawala ang katinuan
病気は治り
怒りは消え
悲しみはなくなり
正気ではいられなくなる
兵士に「この国の病気だ」と暴言を吐かれ、村八分に近い状態になりながらも、しきりに村人に寄り添い、兵士と戦ってきたロレーナに対して、この曲をエンドレスに歌い洗脳する。そして、チョウセンアサガオのドラッグドリンクにより遂に心が折れてしまう。そして、ロレーナも《チョウセンアサガオのブルース(Talampunay Blues)》をノリノリで歌い、兵士になされるがまま犯されてしまう。そして、LA LA LAの旋律も歌い奏でながら殺される。
陽気な曲なのを前に、あまりに凄惨な光景が映され、歌詞には哀愁が漂う。戦いに破れた者の悲哀と戦慄を象徴させるのに、これ以上にない強烈さがありました。
とてつもなく怖い銃の描写
こう聞くと、音楽に頼っている映画に見えるが、決してそんなことはない。顔のシーンこそは上手くないが、映像はいつも通り素晴らしい。翳りに差し込む陽光の美しさ、廃墟から滲み出る悲しき歴史の轍の表現が抜群に素晴らしい。そして、何と言っても、銃の表現がブンブンの心を鷲掴みにした。
みやぞんヘアーの女兵士が、前半こそ「あっみやぞんだ!」とコミカルなキャラクターとして映し出されているのだが、終盤銃をチラつかせて、気まぐれで人を殺していく様子に背筋が凍った。観客は知っている。彼女は簡単に人を殺すということを。だからこそ、フーゴに銃を向けるところが怖い。銃のチャっと音が鳴ると、ヒェーーーと悲鳴をあげたくなりました。
何故、兵士はフーゴを殺さなかったのか?
しかしながら、みやぞんヘアーの女性兵士はフーゴを殺さない。ロレーナをレイプして埋めた場所に連れて行き、銃を渡す。「銃で自殺するんだろ、おら銃やるよ」と圧をかけて去って行き、そこで映画が終わるのだ。ここの胸糞悪さが肝である。フーゴを殺してしまったらそこで終わりだ。フーゴの心を折る為に、真実を語り殺さない。死よりも辛いのは生き地獄であることを、兵士は分かっている。特に詩人。言葉で戦う者から言葉の杖を奪うことこそが、兵士にとっての勝利である。別にただ村にやってきた人だから殺す価値はない。いい子にしているなら、この村にいてもいいし、自殺したいのなら道具(=銃)を渡すから死ぬがいい。全ては自己責任だ。と無言で語る。
《良い子にしているのならば、平和だ》という言葉で、抑圧してきたフィリピン史を表しているクライマックスと言えよう。
最後に…
映画仲間と一緒に挑んだラヴ・ディアス4時間のロックオペラ。そこにはラヴ・ディアスの血反吐の怒りが立ち込める作品であった。いい意味でも悪い意味でも、直接的描写に満ち溢れていましたが、ブンブン観られて大満足です。と同時に、『あるフィリピン人家族の創生』の頃の、本能に任せて画を並べていただけの時代から、理性でもって怒りを語れるようにまで成長したラヴ・ディアスの雄姿に胸が熱くなりました。日本公開するかどうかは微妙なところですが、是非とも日本公開してほしいです。
ラヴ・ディアス監督作記事
・TIFF2016鑑賞記録7「痛ましき謎への子守唄」ラヴ・ディアス8時間の世界
・【解説】「立ち去った女」今観なくて何時観る?金獅子賞受賞のラヴ・ディアス4時間復讐譚
・GW暇だったのでラヴ・ディアスの10時間半映画『あるフィリピン人家族の創生』を観た結果…
・【MUBI×フィリピン映画】『メランコリア』チャリティシスター対AV監督
・【ネタバレ考察】『悪魔の季節』ラヴ・ディアス版『ラ・ラ・ランド』に籠められた憤怒





 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!


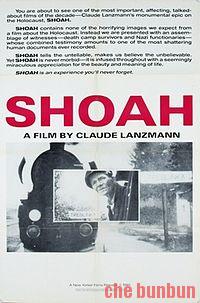




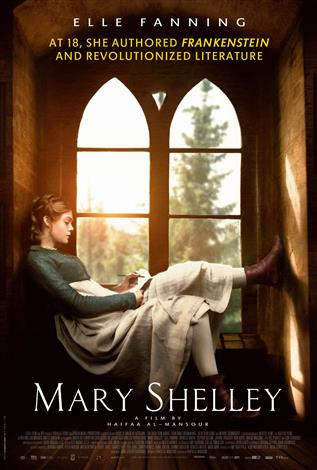








コメントを残す