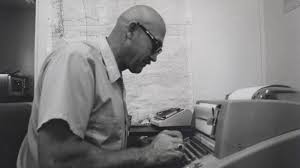見はらし世代(2025)
監督:団塚唯我
出演:黒崎煌代、遠藤憲一、井川遥、木竜麻生etc
評価:75点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
第78回カンヌ監督週間にて日本人史上最年少となる26歳で作品を出品した団塚唯我。彼の長編デビュー作である『見はらし世代』のジャパンプレミアに行ってきた。事前に鑑賞した短編『愛をたむけるよ』が凄まじい演出とイマイチな描写が入り乱れる才能の原石だったのだが、本作ではそれが磨かれ宝石のように輝くものがあった。もちろん、粗削りなところもあれども、少なくとも近年の撮影だけが超絶技巧で、物語の落とし方が弱い日本インディーズ映画群からは一歩秀でたところにある映画だと感じた。危うい部分も込みで好意的に観ることができた。
『見はらし世代』あらすじ
再開発が進む東京・渋谷を舞台に、母の死と残された父と息子の関係性を描いたドラマ。NHK連続テレビ小説「ブギウギ」で俳優デビューを果たし注目を集めた黒崎煌代の映画初主演作で、文化庁の委託事業である若手映画作家育成プロジェクト「ndjc(New Directions in Japanese Cinema)」で短編「遠くへいきたいわ」を発表した団塚唯我のオリジナル脚本による長編デビュー作。
渋谷で胡蝶蘭の配送運転手として働く青年・蓮は、幼い頃に母・由美子を亡くしたことをきっかけに、ランドスケープデザイナーである父・初と疎遠になっていた。ある日、配達中に偶然父と再会した蓮は、そのことを姉・恵美に話すが、恵美は我関せずといった様子で黙々と自らの結婚準備を進めている。そんな状況の中、蓮は改めて家族との距離を測り直そうとするが……。
主人公・蓮を黒崎、父・初を日本映画界に欠かせないバイプレイヤーの遠藤憲一、亡き母・由美子を俳優・モデルとして幅広く活躍する井川遥、姉・恵美を「菊とギロチン」「鈴木家の嘘」の実力派・木竜麻生がそれぞれ演じた。2025年・第78回カンヌ国際映画祭の監督週間に出品された。
PM父、スコープ外に盲目
仄暗い空間に橙のランプが点滅する。カメラは降りていくと道の駅の食堂が映る。群れの運動が入り混じる中で一組の家族へフォーカスがあたり、帰宅までのプロセスを溜めのショットで捉える。どこか不穏でありながら決定的な瞬間はなかなか映らない。黒沢清『Chime』と全く同じ導入で、もしやと思ったら、序盤で確信に変わる場面がある。予告編とは裏腹に黒沢清的演出を軸とした作品であることがわかる一方で、それは黒沢清の迎合に過ぎないのではと不安になる。その危うさを終盤で回避した時点で団塚唯我の鋭さを感じさせる。本作は、建築家(厳密にはランドスケープデザイナー)である父が家族よりも仕事を選び海外へ行ってしまったことをきっかけに家族が崩壊してから10年後の世界を描いている。
黒沢清的演出により、終盤で映画的ファンタジックな演出が挿入される。黒沢清の場合、ファンタジックな世界に転がったら最後、そのまま異界を彷徨う展開になりがちだが、本作はリアリティラインを掴み続ける。それは安易なハッピーエンドを拒絶することであり、まるでクシシュトフ・キェシロフスキ『デカローグ』に近い含みを持たせたラスト。それも投げっぱなしではなく、現実でもトリガーを軸に一歩前進する間延びした人生が続くことを踏まえた落としとなっており好感が持てる。
本作は短編映画『愛をたむけるよ』を拡張したような話である。『愛をたむけるよ』では、母の喪失によりトラウマと貧困を抱えながら前へ進もうとする兄弟を描いた話である。本作も同相の映画でありながら、ミクロな話をマクロな社会情勢と結びつけて語っている。
遠藤憲一演じる父が日本でMIYASHITA PARK建設のプロジェクトリーダーとして活躍していることを軸に、渋谷再開発にて迫害されたホームレスとの関係性と家族の断絶を結び付けている。これは『パラサイト 半地下の家族』での階段の資格を用いた断絶表現に匹敵するほどの慧眼であり、『新しい景色』から『見はらし世代』に変更したことも相まってエッジの利いた視点を提供している。プロジェクトマネージャーは見はらしを良くしてプロジェクトを制御する必要がある。スケジュール、予算、多くのステークホルダーとの関係性を整理して確実にプロジェクトを成功へと導く必要がある。そのためにスコープを定め、ステークホルダーと合意を得ていないスコープ外のことは取り合わないようにするのが仕事である。故に、新入社員や部下からは感情を失ったサイコパスのように思われ恨まれることも多々ある。本作では象徴的な場面として外国人従業員から再開発によってホームレスを迫害してしまうのは可哀想だと言われる場面がある。しかし、プロジェクトマネージャーの立場からすれば、それは行政の仕事である。ビジネスの世界、中間管理職の世界において、可哀想などといった感情で仕事をすることはできない。労働のこうした側面を是正するのは政府や行政がやることであり、一労働者としては話を聞くことしかできないのだ。苦い顔をしながら彼は彼女の話に耳を傾ける。
確かに父はプロジェクトマネージャーとしては成功した。しかし、そういった世界に身を置いているからこそ、スコープの外側で苦しんでいる人々に親密に歩み寄ることはできない。見はらし良い場所から状況は把握しているが、あくまで知った気になっているだけ。それが家族との再会に更なる残痕を刻んでしまうのである。
『愛をたむけるよ』でイマイチに思えた安易な断絶を表現するスプリットスクリーンは多少改善されていた。MIYASHITA PARK建設プロジェクトの過程を様々な質感のイメージでフォトブックを作るように層を形成する場面は面白く観た。一方で3面による表現は、ただイメージを並べただけの面白みに欠ける演出であった。やるなら『ウッドストック』のように異なる運動のイメージを音で繋ぎ、勇気的に建設プロジェクトを捉えるべきだったような気がする。
とはいえ、団塚唯我監督は今後三大映画祭のコンペティションに出品されるような力強さを持った監督であることは疑いようもないだろう。