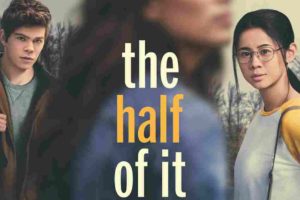I Was at Home, But…(2019)
Ich war zuhause, aber…
監督:アンゲラ・シャーネレク
出演:Thorbjörn Björnsson、エスター・ブス、マーティン・クラウゼンetc
評価:55点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
ここ最近のベルリン国際映画祭は、作家性が露骨に見える変わった作品に監督賞を与える傾向がある。今年のホン・サンス『逃げた女』に始まり、ウェス・アンダーソン『犬ヶ島』、アキ・カウリスマキ『希望のかなた』など。さて、2019年に行われた第69回ベルリン国際映画祭監督賞の話をしよう。日本では数年前にアテネ・フランセで特集が組まれ、MUBIでも積極的に紹介されたことから一部の間で話題となっている監督アンゲラ・シャーネレク。彼の『Ich war zuhause, aber…』がその座を仕留めた。タイトルからもわかる通り、小津安二郎『生まれてはみたけれど』を意識したものとなっている。『私の緩やかな人生』なんかを観ると、小津安二郎やロベール・ブレッソンが好きなのかなと思っていたのだが、今回はタイトルに小津愛をぶつけてきた。そんな作品『Ich war zuhause, aber…』を観たので感想を書いていく。
『I Was at Home, But…』あらすじ
After a 13-year-old student disappears without a trace for a week and suddenly reappears, his mother and teachers are confronted with existential questions that change their whole view of life.
訳:13歳の生徒が1週間、跡形もなく突然姿を消した後、彼の母親と教師は、人生観を一変させる実存的な問いに直面する。
※imdbより引用
家にはいたけれど
荒野に狼がいる。狼はウサギを追い回し、そして仄暗い廃墟の中でウサギを食べる。そしてロバは仄暗く息苦しい廃墟の中で虚無の目をしている。露骨な『バルタザールどこへ行く』愛にびっくりさせられる。アンゲラ・シャーネレクの「私は小津安二郎、ロベール・ブレッソン、だから映画でオマージュする」というある種の開き直りに驚かされる。映画は、極端にセリフを排除している。そのことにより、身体的動きに強度が増す。本作において重要なアクションは接触である。男の子が階段を駆け上がり部屋に入る。すると先生らしき人が出ている。カメラが切り替わると、男の子は人の足に抱きついている。ここで、接触と拒絶が象徴的に描かれ反復するように他の描写へと波及していく。その中でも一番の見所は、すっかり崩壊したある家庭のリビング描写。母親はヒステリックに娘にあたる。娘は手を兄の肩に載せるが、「演技はやめて」と怒る。兄は、母親の元に近づき、手を載せようとするが彼女は振り払う。そこに妹も加勢して母親の辛さを癒そうとするが拒絶する。この一連の流れを通してもう後に戻れない家族の崩壊を象徴させているのだが、インパクトが強くしかも映画的表現となっている。アンゲラ・シャーネレクが、単なる映画愛で賞を獲った監督ではないことがよくわかる。あざとさと作家性のスレスレを疾走し続けるのです。
とはいっても、本作はシェイクスピア『ハムレット』の知識がないとよくわからない作品でもある。数少ないセリフの多くが『ハムレット』からの引用であり、『ハムレット』を現代に置換させ、子どもたちの演劇にまで『ハムレット』要素が波及するので、それを熟知していないと小津安二郎的《移動と静止》の構図、ロベール・ブレッソン的《手》の強度ばかりに目がいき、画だけの映画に見えてしまう。
もちろん、電子音声で会話するおじいさんといった特徴的な人とのバトルシーンは面白かったりするのだが、「よくわからない」という印象が強い作品でありました。
※mubiより画像引用
 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新