ファントム・スレッド(2017)
Phantom Thread(2018)

監督:ポール・トーマス・アンダーソン
出演:ダニエル・デイ=ルイス、
レズリー・マンヴィル、
ヴィッキー・クリープスetc
もくじ
評価:5億点
PTA…子どもいる家庭は、面倒臭いあの学校組織を思い浮かべるであろう。Perfume好きは、Perfumeファンクラブのことだろうと思うであろう。しかし、映画ファンはPTAと聞いて最強の鬼才ポール・トーマス・アンダーソンを頭に浮かべるであろう。ジョン・ヒューズの『大災難P.T.A.』を浮かべる人はいなかろう。さて、あのポール・トーマス・アンダーソンが1950年代のファッション業界をテーマにした作品を作っていると小耳に挟んだ時から、ワクワクが止まらなかった。この新作を観るまで生きねば!と思った。そしてアカデミー賞ではまさかの6部門ノミネート、PTA映画お馴染みの衣裳デザイナーのマーク・ブリッジスが衣裳デザイン賞を受賞した。2ヶ月前ぐらいから、ブンブンの周りの映画友達が口を揃えて、「今年ベスト」、「PTAは神」と語っており、この一週間は「早く観たい、早く魅せてくれ!」と神に祈っていた。そして、土曜日にTOHOシネマズららぽーと横浜で観てきました。
…本当に凄かった。映画職人が作り上げた、精巧すぎるダイヤの彫刻。もはや《1950年代のファッション業界の映画》という要素は彼の前に消滅し、紛れもない《ポール・トーマス・アンダーソンのフェチズム世界》が広がっていた。彼にしか撮れない、完璧すぎて声すら出ない大傑作であった。今日は、そんなPTA最新作『ファントム・スレッド』について語っていく。
※ネタバレ全開記事です。またソフィア・コッポラの『ビガイルド』に関するネタバレもあるので、要注意だ。
『ファントム・スレッド』あらすじ
1950年代のロンドン。有名デザイナー兼仕立て屋のレイノルズ・ウッドコックは、ウェイトレスに恋をした。そしてウェイトレスはウッドコックに誘われ、彼の家に住み込むことになるのだが、、、ダイヤのマチ針が貴方を刺す
ジョニー・グリーンウッドの美しくも、耳がキンキンするような高音の旋律で本作は始まる。この映画は、美しく恐ろしい話であることを冒頭10秒で教えてくれる。そして、物語はデザイナーの家にフォーカスが当たる。監督自らコントロールする舐め回すようなカメラワーク、耽美的な世界観の中で、どうやら残酷な心理劇が展開されているらしい。
「貴方の心に私はいないのね」
と凄腕デザイナー・ウッドコック(町山さん曰く、木彫りのチンチンと言う意味らしい。なんてこった!)のオンナだと思われる方が、日本茶を啜る彼に対して言い放つ。このデザイナーは仕事熱心過ぎて、カノジョを大切にしない男だということがよくわかる。
そして、ウッドコックの姉シリルに「次のオンナを見つけないとね」と彼に言うところから本作は幕を開けるのだ…
ウッドコックは、街を彷徨い、《孤独のグルメ》の井之頭五郎のようにふらっとカフェに入る。そこで、彼はウェイトレスに一目惚れしてしまう。ここから、トンデモナイ目線と目線のドッヂボールが始まるのだ。チラッとウェイトレスを見る。
「ウホッわしの好みだ♡」と笑みを浮かべる。
ポーカーフェイスを貫こうとするが、二度、ドジっ子な彼女をチラ見する。
「よし、キミに決めた!」と、まるで獲物をロックオンしたチーターのような目線で今度はガン見する。
そして、どうやって家にテイクアウトするのかという駆け引きが始まる。注文をする。卵焼き、ベーコン、パンと頼んでいく、もうちょっと彼女と会話したい!という思いから、井之頭並みに欲張って注文する。さらには「ジャムはいちご以外で」と難癖を入れたりする。当のウェイトレスは、顔にコンプレックスを持っているため、こんなダンディな男に甘美な表情で注文されるとは!と満更でもない。そして…ウッドコックはめでたく、彼女の名前(アルマ)を聞き出し、をお持ち帰りすることに成功するのだ。
しかし、このウェイトレス・アルマは知らなかった。ウッドコックはトンデモナイ男だと言うことに。ウッドコックはいきなり、「僕はこの服に母の髪を縫い付けているんだ。だから母を感じるんだ。」と。
ウェイトレスは「うぁマザコンかよ…」と嫌な顔をする。
ただ、謎の引力によって惹き込まれ、彼の家まで来てしまう。すると、いきなり彼女の身体を測り始めるのだ。しかも目つきは、先ほどの甘美な眼を失い、鷲のように鋭い。そして、何故か彼の姉も採寸に参加するのだ。最初は、ダンディな男に触られることに対しエクスタシーを感じていたアルマだったが、
「うーんおっぱいはないね。」と言われ腹が立ってくる。
「なくてすみませんね」と強くウッドコックにいうのだが、彼は
「何を怒っているんだい?完璧な身体だよ」という。
彼の姉も「いやー素晴らしい。完璧だ」という。かくして、《私の奴隷になりなさい》とアルマはウッドコックの新しいミューズ、マネキンとして飼われることになった…
』のように、セリフではなく目線で会話する。ダニエル・デイ=ルイスとヴィッキー・クリープス 、レズリー・マンヴィルの狂気を宿した艶かしい官能の眼による対話に、戦慄と爆笑する作品だったのだ。
そして、この目線の会話劇が実によくできている。前半は、まるで恋愛ゲームのように、アルマが一番難易度の高いキャラクター、ウッドコックをいかにして落とすのかが描かれる。彼女は、仕事熱心で自分のことをマネキンにしか思っていないウッドコックに対してどこか優越感を抱いている。例えば、レストランでの食事シーン。女どもがウッドコックの元へ駆け寄り、「貴方のドレスを着てみたいのよ」と熱弁を振るう。そんな女どもをアルマは、「私は、毎日着てるのよ!」と勝ち誇ったような目で嘲笑う。また、ファッションショーのシーン。ウッドコックは、扉の穴からショーの様子を観ているのを彼女は知っている。だから終始、ドアの穴を見つめ、妖艶さを魅せつけるのだ。
しかし、全くもってウッドコックを落とせる気がしない。どんな攻撃も「効果はいまひとつのようだ」という返答しかこない。アルマは、母親という亡霊(=PHANTOM)に取り憑かれたウッドコックという亡霊に完全に取り憑かれた。そして、彼のような完璧主義者になろうとする。しかし、それすらも無に返されるのだ。
しかし、彼女が、ウッドコックの弱点が《病気》であることを知ってから逆転劇が始まる。毒キノコでもって、彼を病気にさせ、支配しようとするのだ。そして、支配の先に待っている甘い甘い蜜の虜になった、彼女は完全にウッドコックを支配した。そして、その事実に医者もドン引き。さらには、ウッドコック自身、そのキノコプレイを気に入って二人は目出度く結ばれハッピーエンドとなった。
本作は、伝記映画、史劇のように見えて、ごく普通の凡庸な話だ。他の監督が撮ったら90分ぐらいのしょぼい官能ドラマに終わってしまっただろう。しかしながら、PTAのウッドコックとシンクロした、完璧すぎる世界。もはやギャグにしか見えない、主人公たちの顔芸にらめっこに完全にノックアウトされた。そして、レディオヘッドのメンバーなの?と思うほどに、繊細なガラス細工のような愛と官能のメロディ。またタタン、タタン、タタンとウッドコック&アルマの心の高まりを表現したリズムに私の心は完全に溶かされた。ブンブンまでもが、この亡霊に取り憑かれてしまったのだ。アカデミー賞で、何故か6部門もノミネートしてしまったのも納得、映画好き程心酔する作品でした。
オマージュ解説
PTA映画といえば、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権さながらのオマージュにある。特に、本作のラストで追悼の意を捧げているようにジョナサン・デミ監督のファンで、『メルビンとハワード
』をよく引用する。しかし、今回はジョナサン・デミ監督作からの引用は確認できなかった。
オマージュ1:『召使(1963 ジョゼフ・ロージー監督)』
個人的に、本作の骨格は家の間取り含めて、ジョゼフ・ロージー監督のカルト映画『召使』を参考にしているのではと感じた。『召使』とはセレブな男の家に、完璧な召使がやってくるのだが、段々とその召使が男を支配するという内容。アルマがウッドコックの元を離れるように見せかけて、彼のアルマに対する依存を引き出そうとする展開と全く同じことがこの『召使』でも展開されているのだ。そして、特に注目して欲しいのは、階段を使った会話描写。階段の高さを使って、支配関係を演出する描写は、撮影の仕方含めて『召使』と全く同じなのだ。さらにいえば、アルマがサプライズでウッドコックに料理を作るものの、喧嘩をしてしまい戦慄の空間となる描写は、『召使』で男と召使が喧嘩するシーンや召使の心の闇が明らかになるシーンに近い撮影をしている。
もちろん『レベッカ』の方が先に制作されているので、『召使』が『レベッカ』を参考にして作られた可能性はあるのだが、ブンブンはどうも本作が『召使』のアップグレード版にしか見えなかった。
オマージュ2:『ひとりぼっちの青春(1969 シドニー・ポラック監督)』
本作の終盤に登場する、大晦日パーティのシーンは恐らく『ひとりぼっちの青春』を参考にしただろう。本作は、貧しい人々を集めて、耐久マラソンダンス大会を開くという作品。最後の1組になるまで、参加者にマラソンダンスさせるという内容なのだが、いつまでたっても脱落者が出ず、観客まで鬱に陥っていく凶悪な作品だ。このマラソンダンスシーンの狂乱、そして終盤に映し出される廃墟同然となったダンスホールの映し方が本作の大晦日パーティのシーンと似ている。どちらもエンドレスに続く、狂乱への疲労を効果的に演出している。PTAといえば、作品のテーマ性関係なく自分の好きな映画のシーンを隠す監督なのだが、この映画の引用に関しては、物語とシンクロしていた。オマージュ3:『とらんぷ譚(1936 サッシャ・ギトリー監督)』
本作の毒キノコシーンを観て、ソフィア・コッポラの『ビガイルド』を思い出した方も多いはず。恐らくどちらも、サシャ・ギトリー監督の『とらんぷ譚』のエピソードからインスパイアを受けているであろう。『とらんぷ譚』は、金を盗んだ少年が父親に怒られて、夕飯を抜かれるのだが、その夕飯に毒キノコが入っていたため、家族全員死亡してしまうというトンデモエピソードから始まる。『ビガイルド』では、この作品における家族の毒キノコ晩餐シーンの構図を引用していた。本作では、キノコ料理のショットを引用していた。『とらんぷ譚』のこのシーン自体はほんの1分なのだが、観る者の脳裏に焼きつくコミカルさがあるので、機会があれば是非!最後に…
本作は、映画職人ポール・トーマス・アンダーソンの真骨頂と言えるであろう。シンプルなパワーゲームを、セリフに頼らず甘く、シャンパンの風味感じさせる高級感あふれるカメラワークと役者陣の圧倒的顔芸で映画ファンの心をがっちり鷲掴みにした。これは、小説や演劇では決して表現できない圧倒的映画の世界であった。
これは間違いなく、ブンブンのベストテンには入るであろう。素晴らしい神のような作品であった。
彼は次回作、どんな作品を撮るのだろう。前作の『インヒアレント・ヴァイス
』はトマス・ピンチョンの『重力の虹』を撮るための練習だという噂を耳にした。テレビシリーズでもいいから、ポール・トーマス・アンダーソン版『重力の虹』を観てみたい。それまでは、頑張って生きねば!と思いました。






 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!


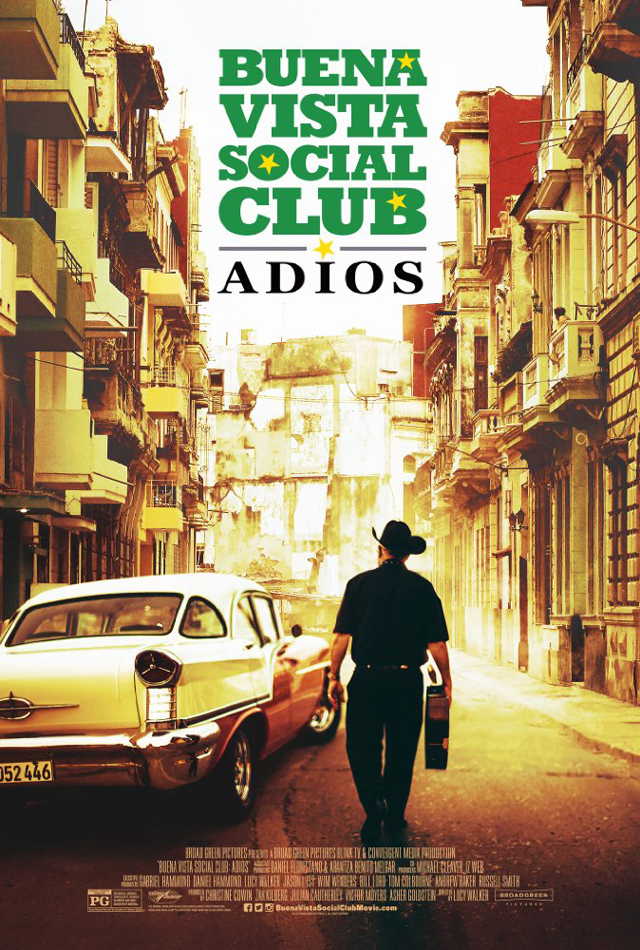



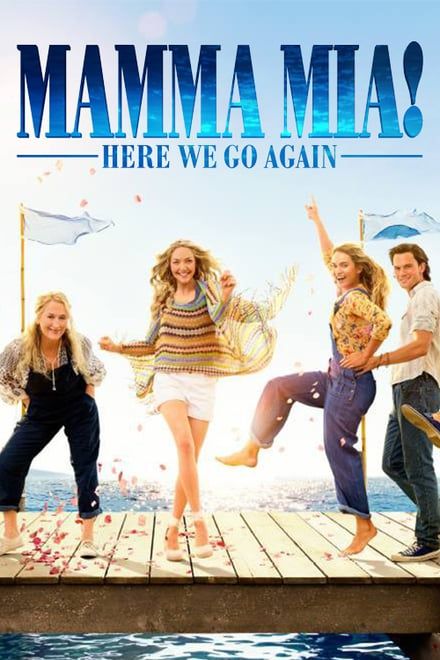
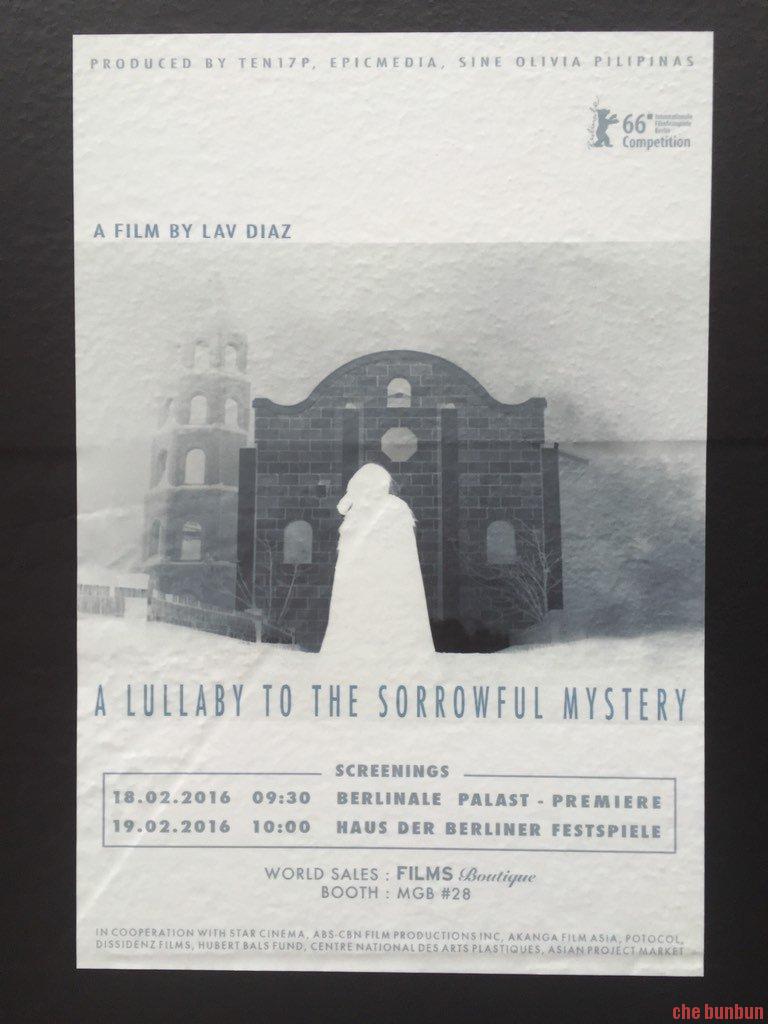








コメントを残す