海を駆ける(2018)

監督:深田晃司
出演:ディーン・フジオカ、太賀、
阿部純子etc
評価:85点
『淵に立つ』で第69回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞を受賞し、先日フランス文化省から芸術文化勲章のシュバリエが授与されることも決まった日本インディーズ映画界のホープ深田晃司。毎作、他の日本映画とは雰囲気が違うアーティスティックでビザールな映画を生み出す彼の新作は、スマトラ島のバンダ・アチェで撮られた。その作品の名は『海を駆ける』。深田晃司映画ファンのブンブンは、何か凄いオーラをこの作品から感じ取った。そして、公開初日にTOHOシネマズららぽーと横浜で観て来ました。
まさかのMX4Dスクリーンでの上映w
深田晃司ワールドを堪能するぞ♪ pic.twitter.com/EKkaZfwmQz
— che bunbun (@routemopsy) 2018年5月26日
今回、映画仲間から解説してほしいとリクエストがありましたので、ネタバレありで、本作について考察していきます。
『海を駆ける』あらすじ
スマトラ島のバンダ・アチェでNPO法人災害復興業務に携わっている貴子は、現地人と協力して、スマトラ島沖地震に関するドキュメンタリーを撮っている。そんなある日、海に日本人と思われる男が流れ着いた。彼は記憶を失っていた。とりあえず《Laut(=海)》と名付け、預かることにするのだが、周りで不思議なことが頻発する…世界相手に戦える脚本
本作を鑑賞した直後、ブンブンの震えは止まらなかった。ここまで、高度で複雑な脚本と映画としての面白さを両立させていたとは予想だにもしていなかったからだ。冒頭、美しいアチェの海が映し出され、クレジットが流れる。すると、奥から人影が見えてくる。あまりに神秘的なディーン・フジオカ登場シーンに「なんだ?なんだ?」と画面に釘付けとなる。
そして、場面は変わる。日本人とインドネシア人がドキュメンタリーを撮っている。それがスマトラ島の地震被害をテーマにしたドキュメンタリーらしい。なるほど、東日本大震災による傷跡を、スマトラ島の津波による被害から客観的に捉えようとしているのか。面白い視点だ。とワクワクしてくる。
しかし、何故か途中から、この映画の正体が濃霧に覆われて見えなくなってしまうのだ。
ディーン・フジオカ扮する謎の男《Laut》は、NPO法人の貴子とその仲間たちの周りをふらついているだけ。Lautがフラフラと彷徨っている側で、貴子ファミリーは何気ない日々を過ごす。息子のタカシは、インドネシア人のアイデンティティーを確立してしまっているので、夏目漱石や宮沢賢治、三島由紀夫の小説を読んでもパッとしない。夏目漱石がI love you.を「月が綺麗ですね」と訳したエピソードを聞いても、別世界の出来事過ぎて共感できない。親戚のサチコは、タカシの友人のインドネシア人に好かれ、デートに誘われる。彼から「月が綺麗ですね」と言われ、困惑する。一方、貴子とドキュメンタリーを作っているイルマは、足を怪我した父親から日本人と接触していることについて文句を言われ悩んでいる。歴史、自然、アイデンティティーの渦の中で、ふわふわと白昼夢を彷徨うような人々の横で、何故か《Laut》は無作為に人々を生かしたり殺したりするのだ。
彼には全く善悪もなければ感情もない。あるのは、ある人の死、または復活のみだ。そして《Laut》の不思議な行動は衝撃的な展開を迎える。終盤、いきなり《Laut》が貴子を殺すのだ。試写会で本作を観た、映画仲間が「よくわからない、解説頼む」と求めてきた箇所がまさしくこの部分だ。なんで、主人公であり、全くもって死亡フラグが立っていない彼女が死なねばならなかったのか?
実は、この映画、《Laut》に合理的な理屈を求めようとすると深遠なる泥沼に引きづり込まれる仕組みとなっている。もっとシンプルに、目の前のことを観察すると答えが見えてくるのだ。
さてブンブンの答えを語るとしよう。《Laut》は文字通り《海》を象徴した存在なのだ。アチェの海は綺麗だ、美しい。しかしながら、スマトラ島沖地震で発生した津波は、無残にも人々の命を奪った。この美しさと残酷さをディーン・フジオカ扮する《Laut》に託しているのだ。ここで重要となるポイントは、《Laut》が無差別に人々を生かし、殺しているということ。津波は、善人、悪人、老若男女構わず人々の命を奪った。故に、《Laut》の前で子どもたちは死に絶え、主人公である貴子ですら死んでしまったのだ。
海から化身のように現れた《Laut》は津波のようだ。津波が、多くの人々を殺す一方、思いがけない邂逅を生み出すように《Laut》も混沌の渦へ貴子ファミリーそして観客もろとも引きずり込むのだ。このような神秘に取り憑かれた深田晃司監督は、凄惨な物語であるにも関わらず、詩的で明るくこの海を駆け抜けてみせた。やはり、ブンブンの目に狂いなく、トンデモナイ傑作であった。
それにしても…
貴子とタカシの夏目漱石トークシーンがとてつもなく面白かった。
夏目漱石の『それから』を読んでいるタカシは貴子に「この人知ってる。お札に描いてある人でしょ」という。
そして続けさまに「あと猫!(『吾輩は猫である』のこと)」と言う。
その後、貴子は「それから?」と訊く。
ブンブンの目が宝石のように輝いた名シーンでした。
深田晃司監督作レビュー
・【ネタバレ解説】「淵に立つ」食事シーンと赤の使い方を徹底解説!





 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!


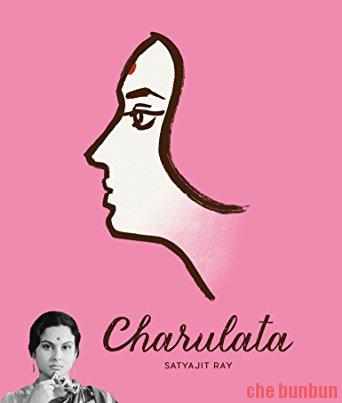













コメントを残す