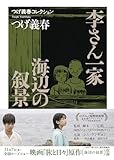旅と日々(2025)
Two Seasons, Two Strangers
監督:三宅唱
出演:シム・ウンギョン、堤真一、河合優実、髙田万作、佐野史郎、斉藤陽一郎、松浦慎一郎etc
評価:100点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
第60回ロカルノ国際映画祭で 小林政広『愛の予感』が最高賞を受賞していらい18年ぶりに日本映画が金豹賞を獲った。つげ義春の短編漫画「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」を原作とする三宅唱『旅と日々』は、彼の原点回帰ともいえる作品だと耳にはしていたのだが、実際に鑑賞すると『やくたたず』『Playback』というよりかは『THE COCKPIT』からの派生ともいえる内容であり、その応用の凄まじさ。アレクサンドレ・コベリゼ『枯れ葉』やアミルレザ・ジャラライアン『ノアの娘』、チャン・リュル『春の木』などといった近年のアート映画の傾向に即した時代性も踏まえた一本であった。
『旅と日々』あらすじ
「夜明けのすべて」「ケイコ 目を澄ませて」の三宅唱が監督・脚本を手がけ、つげ義春の短編漫画「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」を原作に撮りあげたドラマ。「怪しい彼女」「新聞記者」のシム・ウンギョンを主演に迎え、行き詰まった脚本家が旅先での出会いをきっかけに人生と向き合っていく様子を、三宅監督ならではの繊細なストーリーテリングと独特の空気感で描き出す。
強い日差しが降り注ぐ夏の海。浜辺にひとりたたずんでいた夏男は、影のある女・渚と出会い、ふたりは何を語るでもなく散策する。翌日、再び浜辺で会った夏男と渚は、台風が接近し大雨が降りしきるなか、海で泳ぐのだった……。とある大学の授業で、つげ義春の漫画を原作に李が脚本を書いた映画を上映している。上映後、質疑応答で学生から映画の感想を問われた李は、自分には才能がないと思ったと答える。冬になり、李はひょんなことから雪に覆われた山奥を訪れ、おんぼろ宿にたどり着く。宿の主人・べん造はやる気がなく、暖房もまともな食事もない。ある夜、べん造は李を夜の雪の原へと連れ出す。
脚本家の李をシム・ウンギョン、宿の主人・べん造を堤真一が演じ、河合優実、髙田万作、佐野史郎が共演。スイス・ロカルノで開催された第78回ロカルノ国際映画祭のインターナショナルコンペティション部門に出品され、日本映画としては18年ぶりとなる最高賞の金豹賞を受賞した。
都会の日常における匿名性と旅の非日常における匿名性について
都会のビル群が映し出される。それぞれのビルが個として聳え立ちながら都会という空間の中で融和し群として背景を形成している。個がそこにありながら匿名的な存在に押し込められていることを強調するように、次のショットでは狭い一室で韓国人女性がハングルで文章を書き始める。現実とは異なる音がオーバーラップし、文章の世界へと映画は没入していく。「どこ」といった固有名詞から離れた夏の海。目的もなく彷徨う人々が描かれる。ただそこにいる。匿名的な他者として自由な時間に身を投じる。その空間は孤独に覆われているわけではない。突発的にヒトとヒトとが一期一会の会話を交わす。外国人女性が「あなたの写真を撮ってもよいか」と母国語と身振りで話しかける。目の前の運動を推察し、ポーズをとるのである。また、別の一期一会では、男女の向ける眼差しの先に映る情景をフレームの外側に追いやりながら対話を重ねる。そこには、暇に耐え切れない現代人の特性に対する指摘が挿入される。このようなやりとりは非日常な手触りを有しており、旅に彩りを与える。
つまり、『旅と日々』は都会の日常における匿名性と旅の非日常における匿名性を交差させる試みなのである。狭い一室から世界を広げる手法は、まさしく『THE COCKPIT』で音楽が創造される瞬間を捉えた三宅唱ならではの視点なのだが、本作はそこに幾重もの層を上塗りし、映画に深みを与えている。
彼女が書いた文章の世界は映画の脚本であり、部屋の一室から時空間を超えて完成した映画が大学で上映される時間軸へと結びつけられるのだ。映画制作の関係で、彼女の生み出した虚構は実際の撮影により具象化される。現実空間に展開される虚構として捉えられ、人々に提示される。しかし、それ自体は脚本というコードによって進行しているため、非日常でありながら日常的ルーティンに囚われている。その様を「言葉に縛られている」と彼女は評価し、非日常を求めて宿すら決めていない旅へと出る。言葉に縛られている様は、韓国人故に韓国語と日本語の狭間で葛藤し遅効的に発せられる言葉にて表現される。若干の危うさはありつつも、映画の世界における外国人との対話でバランスが取られている点は注目であろう。
最後に着目すべきは、写真の存在にある。脚本の世界で、博物館の写真に眼差しが向けられる場面がある。その土地の個人にフォーカスがあたっているのだが、その個人はその地の営みを象徴する存在として扱われ、個から群なる存在へと押し込められている。つまり、写真に写る人物は匿名的な他者なのである。
彼女はあてどない旅に出る。そこで、べん造と出会う。そこで落とす/見逃す/捨てる行為を通じて匿名的他者になりながら、目の前の事象を固有のものとし捉え、言葉から自由になる経験を得る。具体的には、彼女はカメラを落とすことで、目の前の事象、個人を匿名的他者、背景として無意識に消費してしまう状況を免れている。次に、べん造が「ユーモアのある話が好きだ」と語る場面がある。だが、その後に訪れる鯉にまつわるユーモラスな事象に関しては双方ユーモアだと気づかず、岡目八目な観客だけが受容する構図となっている。その後の突然なる終わりも含めて、物語としてその地を受容してしまう様が回避される。そして、べん造を取材し映画の脚本にすることを破棄することによって、逆説的にべん造をべん造個人として接することに成功している。
三宅唱は匿名的他者が旅を通じ、異なる匿名的他者になり心理に広がる複雑さと折り合いをつける過程をメタ的に描く。旅先での一期一会の豊かさを通じて、タイパ/コスパの世界が失ってしまった豊穣な時へ賛美を送りつつ、他なる土地の人々を匿名的他者として消費してしまっている危うさを批判しながらあるべき自由な時間を探求する冒険に私は涙したのであった。
※映画.comより画像引用