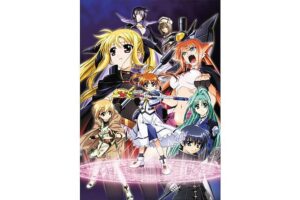Dry Leaf(2025)
監督:アレクサンドレ・コベリゼ
出演:Giorgi Bochorishvili、Irina Chelidze、Vakhtang Fanchulidze etc
評価:90点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
先日、第78回ロカルノ国際映画祭の受賞結果が発表された。三宅唱監督『旅と日々』が最高賞を、空音央監督『まっすぐな首』が最優秀短編映画賞を受賞したことで日本では歓喜に包まれた。一方で、他の受賞作の情報は全く流れてこない。こういう時こそ、他の部門にも目を向けるべきである。実際に今回のロカルノ国際映画祭は当たり年だったようで、中国でキャリアを積もうとするベラルーシ人モデルがモルグの男と惹かれる『WHITE SNAIL』や東京国際映画祭で『私に構わないで』が紹介されているハナ・ユシッチ新作『GOD WILL NOT HELP』、アッバース・ファーディル新作『TALES OF THE WOUNDED LAND』が受賞している。どれも今年の東京国際映画祭に来る可能性を秘めている作品である。そして、その受賞結果の中に『ジョージア、白い橋のカフェで逢いましょう』アレクサンドレ・コベリゼ新作『Dry Leaf』の名前があった。サッカー場を撮影する女が失踪し、父親が幽霊と共に彼女の轍を巡る3時間を超えるこのロードムービーがスペシャル・メンションを受賞していたのだ。実際に観てみると、想像以上にチャレンジングな、もはや実験映画の領域ともいえる意欲作であった。ボールの軌道を予測不能にする蹴り方を示すサッカー用語から取られているだけあってトンデモナイ変化球だったのだ。
『Dry Leaf』あらすじ
A father searches for his daughter Lisa, a sports photographer who disappeared while documenting rural soccer fields across Georgia, joined by her enigmatic best friend.
訳:ジョージア州の田舎のサッカー場を撮影中に行方不明になったスポーツ写真家の娘リサを、謎めいた親友と共に捜す父親。
三宅唱旋風の裏で荒れ狂う3時間のガビガビVLOG映画
オープニング映像で強烈な違和感を抱いた。イメージがガビガビなのだ。YouTubeの144pレベルの低解像度となっているのだ。ネットワークが悪いのかと設定を自動から720pに変更し確認する。しかし、状況は変わらない。この時点で「長い旅になりそうだ」と思った。そして、アレクサンドレ・コベリゼは『ジョージア、白い橋のカフェで逢いましょう』ではなく、『Let the Summer Never Come Again』の監督であったことを思い出した。彼の長編デビュー作『Let the Summer Never Come Again』は低解像度の携帯電話のカメラで撮影された202分ある作品だ。セリフはほとんどなく、人生の何気ない日常を思い出したかのようなイメージの表象として低解像度の映像が用いられている。本作はこの技法を発展させたものとなっている。
スポーツ写真家であるリサから「わたしを探さないで」と手紙が届く。しかし、父のイラクリは心配してリサの編集者に連絡を取る。彼女はどうやらジョージアの廃墟同然のサッカー場にまつわるフォトエッセイを作ろうとしていたらしい。イラクリはリサの知り合いでもあるレヴァンと共に、彼女の轍を辿る旅に出る。ここで重要なことは、レヴァンは幽霊のような存在であることだ。なぜなら、イラクリが車に乗り隣に話しかけるも、そこには誰もいない。そして、レヴァンは受け答えをしているからだ。
最近、ホン・サンスが部分ピンボケ映画『水の中で』で映画における印象派的役割を模索していたが、『Dry Leaf』はより深い次元で映画が表現するイメージの拡張に成功しているといえる。まず、バキバキにキマッたショットながら画質が悪すぎてフラストレーションを引き起こす様は、印象派が元来、美術界において悪口のラベルとして扱われ一部で嫌悪されていた状況とシンクロしている点にある。そこには、従来型の手法に対する批判的な側面がある。映画業界が4K、8K、IMAXと高画質な映像を求める中でノスタルジックなタッチとしてフィルムの質感で描くアプローチは定石である。しかし、デジタルの時代も30年近く経っている。デジタルの映像にもフィルムのようなざらつきが存在し、それを通じた過去の表現ができないか?この新機軸は『水の中で』になかったものといえる。そして、低画質によってビット単位で光の粒子が露見し、低画質の世界の奥に広がる絶景へと意識を向ける様は印象派を鑑賞する態度に近いものがある。つまり、本作のアプローチは映画で印象派をやる本質に迫った作品なのだ。
このアプローチは映画と密接に関わってくる。ストーリーはありふれた「他者の轍を辿るロードムービー」である。これは過去を辿ることと同義であり、他者が踏んだ地と同じ場所に立ち過去へと想いを馳せる中で自分を見つめ直す活動となっている。過去を振り返ることはノスタルジックなことである。脳裏には朧気ながらも恍惚な風景が広がるものである。さらに今回の失踪者は写真家なので、彼女の撮影した当時の情景/今いる場所/彼の脳裏で再現される当時の場所が折り重なり心が複雑に揺さぶられていく。だからこそSony Ericssonでレンダリングで行い2Kで上映する、今の映画だけれども昔のホームビデオのようなイメージに意味があるのだ。
また、本作はコロンブスの卵一辺倒な映画ではないことも言わねばならない。本作において廃墟同然のサッカー場といったモチーフが重要な役割を果たしている。このモチーフはヴィクトル・エリセ『瞳をとじて』のネットが張られていないゴールに記憶と記録の中間を象徴させる手法に近いのだが、本作では子どもたちが遊ぶ状況も捉えられている。実際にサッカー場へ行く、そこで活動が行われているかどうかわからない宙吊りの中でふと営みが現出する。まるで記憶がふっと現実のように降りてくる感覚があり、本作における霊的存在と実体の曖昧さ。旅をする、匿名的他者として彷徨う自分自身もまた幽霊のようであり、それが物語を放置したかのように揺蕩う心象風景と強固に結びつくのである。