屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ(2019)
Der Goldene Handschuh
監督:ファティ・アキン
出演:ヨナス・ダスラー、マルガレーテ・ティーゼル、カーチャ・シュトゥットetc
評価:40点
おはようございます、チェ・ブンブンです。ファティ・アキンをご存知だろうか?
『愛より強く』で第54回ベルリン国際映画祭金熊賞、『そして、私たちは愛に帰る』で第60回カンヌ国際映画祭で脚本賞、『ソウル・キッチン』で第66回ヴェネツィア国際映画祭で審査員特別賞を受賞36歳で3大映画祭を制覇した監督である。そんな彼はロードムービーからコメディ、ドキュメンタリー、社会派ドラマと作風をコロコロ変える作家で、ソダーバーグに匹敵する作家性から逃れようとする監督である。そんな彼が1970年代に存在した殺人鬼を描いた作品を発表。昨年のベルリン国際映画祭を賛否両論の渦に包んだ。カルト映画の王ジョン・ウォーターズは2019年のベストテンに本作を入れていたのだが、ファティ・アキンにラース・フォン・トリアー的映画は作れるのか?と不安になるものがある。そして実際に観ると、非常に困った作品でありました。
『屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ』あらすじ
「ソウル・キッチン」「女は二度決断する」のファティ・アキン監督が、1970年代のドイツ・ハンブルクに実在した5年間で4人の娼婦を殺害した連続殺人犯の日常を淡々と描いたサスペンスホラー。第2次世界大戦前に生まれ、敗戦後のドイツで幼少期を過ごしたフリッツ・ホンカ。彼はハンブルクにある安アパートの屋根裏部屋に暮らし、夜になると寂しい男と女が集まるバー「ゴールデン・グローブ」に足繁く通い、カウンターで酒をあおっていた。フリッツがカウンターに座る女に声をかけても、鼻が曲がり、歯がボロボロな容姿のフリッツを相手にする女はいなかった。フリッツは誰の目から見ても無害そうに見える男だった。そんなフリッツだったが、彼が店で出会った娼婦を次々と家に招き入れ、「ある行為」に及んでいたことに、常連客の誰ひとりも気づいておらず……。2019年・第69回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品作品。
※映画.comより引用
カリスマ性0の男の日常を覗いてみないか?
フリッツ・ホンカが夜な夜な倒れた女を運ぶ。少女に目撃されるが、シッシと追いやる。そして女の死体の解体ショーが始まる。グロテスクなノコギリを女の首根っこにかけるが、気合いを入れても躊躇してしまい。酒を飲み始め、ようやく解体が始まる。淡々と映し出される解体ショーは、男の日常を捉えたドキュメンタリーのように展開されている。しかし、グロテスクな描写に慣れていないのか、肝心な解体は壁の隅から映すだけのものとなっている。
こうしてフリッツ・ホンカのグロテスクな日常が幕を開けるのだが、それが非常に退屈だ。行きつけのバー“ゴールデン・グローブ”と自宅を行き来するだけなのだ。男はバーで女を口説こうと「あそこのネェちゃんに一杯」と店員に声をかけるのだが、女は「あんたブスね」、「キモい」と断られてしまう。しかし、彼は諦めない。そうこうしているうちに、幸が薄い女が、縁を感じ彼の盃を受け取ってくれる。そして、彼は彼女をお持ち帰りするのだ。底辺が、さらなる底辺の女を奴隷のように扱う。そして女は、彼に見捨てられたくないのでDVさながらの状況に追い込まれても彼に尽くす。
それを、ラース・フォン・トリアーやミヒャエル・ハネケならスタイリッシュに撮っているものをひたすらつまらなそうに撮り続けるのだ。だから映画的快感は限りなく低い。しかし、一方で救いようのないどん底の人生をありのまま映し出すことで、真の多様性を見出そうとしている。ポリティカル・コレクトネスの観点で観ると大正解な作品となっているのだ。殺人鬼を過度に誇張しない。一定の距離から殺人鬼と向かい合う。
ファティ・アキンの腕前は確かなものである。
とは言っても、やはりつまらないものはつまらない。非常に困った作品でありました。
 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!














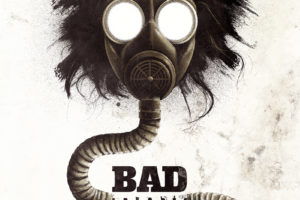







コメントを残す