火口のふたり(2019)
監督:荒井晴彦
出演:柄本佑、瀧内公美
評価:80点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
Filmarksのオンライン試写会で8/23(金)公開『火口のふたり』を一足早く拝見しました。本作は、映画芸術の問題児・荒井晴彦監督作。恐らくは、2019年ベストテン1位は本作であろう。正直、ブンブンは荒井晴彦映画の良さが分からない。強いて言えば『嗚呼!おんなたち 猥歌』が良かったぐらいだが、あれは内田裕也のライブシーンが好きなだけで脚本に惹かれたという訳ではない。だから口悪く言えば、嫉妬深い老害おじさんというイメージしかないのですが、これが非常に面白かった。
『火口のふたり』あらすじ
直木賞作家・白石一文が男と女の極限の愛を描いた小説「火口のふたり」を、柄本佑と瀧内公美の共演で実写映画化。「幼な子われらに生まれ」「共喰い」などの名脚本家で、本作が監督第3作となる荒井晴彦が監督・脚本を手がける。東日本大震災から7年目の夏。離婚、退職、再就職後も会社が倒産し、全てを失った永原賢治は、旧知の女性・佐藤直子の結婚式に出席するため秋田に帰郷する。久々の再会を果たした賢治と直子は、「今夜だけ、あの頃に戻ってみない?」という直子の言葉をきっかけに、かつてのように身体を重ね合う。1度だけと約束したはずの2人だったが、身体に刻まれた記憶と理性の狭間で翻弄され、抑えきれない衝動の深みにはまっていく。
※映画.comより引用
荒井晴彦の2010年代史
これは荒井晴彦が放つ2010年代史だ。それもたった二人の男女の会話をフィリップ・ガレル映画のように魅せることで表現する一風変わった2010年代史なのだ。
結婚式のため、昔の女である佐藤直子(瀧内公美)に会いに行く男・永原賢治(柄本佑)。レストランでふたりは空白の7年を語り始める。永原賢治は印刷会社で働いていたのだが、2011年の東日本大震災と、それにより相次いで起こるイベント自粛によって会社が倒産し、会社を移るもののうまくいかなかった。今では妻にも逃げられ、一人プータローになっている。そんな彼に、佐藤直子は「あの頃に戻ってみない」と肉欲の関係を迫る。
白黒だった肉欲の想い出がたっぷりと詰まった写真は、色彩を帯びてくる。それは灰色だった彼の2010年代史に最後の光を魅せるものであった。たった五日間だけのファンタジーが画面に広がっている。
荒井晴彦の作品はよく分からないものが多いのだが、初めてわかった気がした。それはブンブンも肌に感じながら生きた2010年代という陰鬱とした雰囲気と肉欲、写真の使い方が伝統工芸品のような光沢を持っていたせいであろう。とにかく面白い。
色彩を帯びてくるあの頃の青春は、No Country for Old Men(老人に帰る場所がない)という残酷な現実を突きつけてくる。あれだけ元気だった体にもガタがきており、永原の先っちょは腫れてしまい、「うー痛い」と悲鳴をあげる。佐藤もゲリラゲリに見舞われ、情けない醜態を魅せてしまう。それでもふたりは互いの空白を埋めるように交わって行く。背徳感を得るためにバスの中でも喘ぎ声を漏らす。そうやって、東日本大震災以降、誰の人生をも歩いてきていない、自分の人生すら歩けなかったものが、微かに自分の軌跡を創り出すそこに美しさを感じた。そしてギョッとするラストによって閉じられる円環は、この官能のファンタジーをより一層強いものへと昇華させた。
 ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!








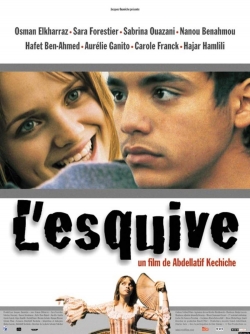

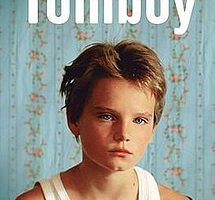

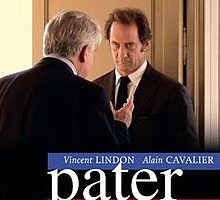









コメントを残す