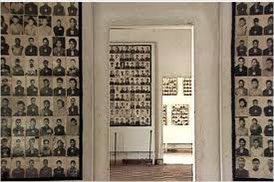ル・ラック(2025)
Le Lac
監督:ファブリス・アラーニョ
出演:クロチルド・クロ、ベルナール・スタムetc
評価:30点
2025年7月4日(金)、新宿歌舞伎町の王城ビルにて開催された《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展へ足を運んだ。朝一だったので、貸し切りに近い状態でイメージの洪水に迷い込んだ。その空間はリミナルスペースのような趣があった。彷徨いの中でペルシャ絨毯の前にてMacBook Proで作業をしているおじさんがいた。1m前で私が立っているにもかかわらず、彼は気にせずタイピングをしている。明らかに不釣り合いな場所で。現実においてNPCとエンカウントしてしまったかのような異物さがリミナルスペース感をより際立たせていたのだが、このおじさんこそがファブリス・アラーニョだった。
『ル・ラック』あらすじ
晩年のジャン=リュック・ゴダールの作品で撮影監督を務め、2025年に東京で開催された「GODARD TOKYO 2025|ゴダール展」のキュレーションを務めたファブリス・アラーニョの監督デビュー作。広大な湖を舞台に、数日間におよぶヨットのセーリング・レースに挑戦する中年のカップルを描く。ふたりは激しい嵐に見舞われながらも執念でレースを続行するが、彼らが何者なのか、また、こうまでしてレースを続ける理由は何なのかは明確には説明されない。台詞は最小限に抑えられており、驚異的に美しいカメラワークとサウンドで観客を魅了する作品である。ロカルノ国際映画祭コンペティションで上映され、ジュニア審査員賞とエキュメニカル賞スペシャルメンションを受賞した。
※第38回東京国際映画祭サイトより引用
自然をコントロールする運動への眼差し
ジャン=リュック・ゴダールの右腕である彼の監督デビュー作が第38回東京国際映画祭にて上映された。ヨットレースに関する映画とのことだが、宣材写真を観るとアルベール・セラの『パシフィクション』を彷彿とさせるものがあり、単なるレース映画ではないことは自明であった。そして、私はTOHOシネマズ シャンテにてその世界に飛び込んでみた。
ゴダールが『ヌーヴェルヴァーグ』をはじめとし、《手》のショットに拘っていたように本作も冒頭で《手》が強調される。湖のイメージと重なるような《手》。それは水へと触れる感触ではなく、スクリーンの中に広がる世界へと触れようとする《手》。ベルイマン『仮面/ペルソナ』における、少年がスクリーンへと伸ばすような質感を抱いている。
そして、レースが始まると、予定調和から外れた自然をものにしようと手を使う人間の営みにフォーカスが当たる。なるほど、ロバート・レッドフォードがひたすら自然を相手にする『オール・イズ・ロスト 最後の手紙』と似たようなコンセプトであることがわかる。
ゴダールの右腕だっただけに、このコンセプトには「無」も扱われる。ゴダールは「黒画面」にて、我々観客の脳内イメージへと語り掛けた。対してファブリス・アラーニョは、聴覚を奪う。無音の中、観客はイメージへと注意を向けるのである。これはジョン・ケージが「4分33秒」で行ったものとは異なる。20世紀前半に制度として確立されたクラシック音楽の形式が崩壊し、形式による必然的な形で秩序立てられた音楽に対する批評として、偶発的な音に着目するコンセプトとしてジョン・ケージ「4分33秒」は位置づけられっている。本作の無音は、サイレント映画時代の純粋なアクションへの好奇を掻き立てるものとして機能しているのである。
このように考えると、ゴダールの理論を継承する映画として『ル・ラック』は成功しているように思えるが、中年カップルの過去や心象世界を表現するヨット外のイメージがノイズとなってしまっていた。自然/人工の関係性から運動を見つめる作品であるのなら、静謐な世界で横たわるカップル、部屋に対する眼差しは不要であっただろう。純粋な自然/人工の関係を描いた先行例として『オール・イズ・ロスト 最後の手紙』がある以上、本作の目論見は失敗に終わってしまったように思える。