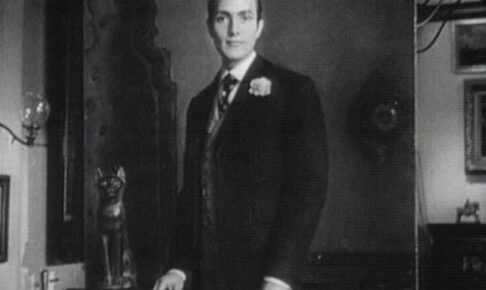ドリアン・グレイの肖像(1945)
THE PICTURE OF DORIAN GRAY
評価:70点
「ライフ・ワーク・バランスねぇ……美術への関心も良いけれどワークにも集中してもらわないと」
ステークホルダーのXは、溜息交じりに嫌味っぽく言い放つ。冷汗が噴出しそうになるのをグッと押さえる。アイスコーヒーの氷が融解する際のカランといった音にも敏感になる。突然、カフェに呼び出され、管理職としての意気込み、5年後どうなりたいのかをXから問われ狼狽し、絞り出すようにして「特に今のところは考えてないです。ただ、プライベートでやりたいことがあるので、そのためにも真面目に管理職に取り組もうと思います」と言った結果がこれである。とある政治家のようにライフ・ワーク・バランスを捨てる気はない。ワークはライフの奴隷である。所詮、ベーシックインカム、暇つぶし、創作のネタ探しの場に過ぎないのだ。それに、ワークに専念しろと言うだけの賃金をお宅は支払っていないだろう。そんな環境で5年後のことを尋ねたところで、面従腹背、取り繕われた無意味な回答しか出てこないであろう。会社に縛るための口実が出るか出ないかの話でしかない。私が美術検定1級を受けようとしている点に対し、同席していたXの部下Yが「Xさんは美術に詳しいんですよ」とゴマを擦る。雑談デッキであれば太刀打ちできる、美術性の違いがあると思うので、試しにSOMPO美術館で開催中の「モーリス・ユトリロ展」の話をする。また、現代美術、特に抽象的な作品が好きなのでブランクーシの名を挙げるがXは知らなかった。
彼はしたり顔で「現代ねぇ…現代をどのように定義するかが重要ですね」と語った上で、「オスカー・ワイルドについて知っているか」と問う。
「『サロメ』の人ですよね、まだ読んだことないんですよ。興味はあります。オススメ作品教えてください。」と言ってみた。
すると、「オスカー・ワイルドを知らないと芸術について語れない」と言い始めた。どうやら彼は作品論というより、彼の生き様を通じた美術観に関する理論を持っているらしい。なるほど、これは厄介な美術愛好家ってわけだ。じっくり話したら面白そうだし、現代美術に関してはカール・アンドレ論を持っているので議論したいところであるが、あくまで管理者面談だったのでこれ以上は踏み込まず、結局X部長の好むトークデッキが読めずに終了した。
会社帰りに青山ブックセンターで「ドリアン・グレイの肖像」を購入して読んだ。序文にノックアウトされた。
芸術家は美しいものを創造する。
芸術家は作品だけを見せ、作者の姿は見せないよう心がけている。
批評家とは、美しいものから受けた印象を、別の手法や新しい素材で伝えられる者である。
オスカー・ワイルドはどうやら表層批評派な方らしい。今や芸術家はメディアの前に出てナラティブを語ることで作品に導線を引く。批評家もバックグランドを中心とした批評がメインとなりつつある。そんな時代に、オスカー・ワイルドの芸術論はギクリとさせられるものがある。Xが私に読機を与えてくれたことに感謝だ。
内容も今に通じる話であり、今風に語るとするならば推しのVTuberのファンアートを描く者が、絵に自分の欲望を投影させ、実体との乖離が生じている存在と配信でコメントして実体をコントロールしようとする存在がいる中で、実体が婚約し心理的混乱を招く。しかし、女優である婚約者が結婚を機に情緒が乱れ、演技がヘタクソになる中で実体にも変化が起こる。この複雑な関係性が癖になる面白さといえる。推し活文化に通じる話ではと思って途中まで読んだ。プライム・ビデオに映画があったので、それにも触れてみることにした。
『ドリアン・グレイの肖像』あらすじ
1885年、富と美ぼうにめぐまれたドリアン・グレイは、画家ホールウォードに肖像画を書かせた。それは素晴らしい画で、まるで生きているような不思議な魅力があった。画家の姪にあたる少女グラディスは、まだ渇かぬカンヴァスのすみに、伯父の署名のそばにGという字をいたずらに書いた。自分の肖像画に見とれながらドリアンは、この画の若さを僕がいつまでも保つことが出来たならと一言をいうと、彼の友人で皮肉屋のヘンリー・ウォットン卿は、エジプトの黒ネコの像の前で願えば君の願はかなうぜという。数日後ドリアンはロンドン下町の歓楽街を歩いていた。彼の耳にはヘンリー卿の言葉-生活を享楽しろよ、あらゆる機会をのがさずにという言葉が耳から離れなかった。下品なミュージックホールで歌っているシビル・ヴェースを彼は美しいと思った。彼女と結婚しようと思ったドリアン卿と画家をさそって彼女の舞台をみせた。卿は言った、結婚の必要はない、肖像画を見に来いと誘って来たら帰さなければいいんだ。卿の言の如く、ジビルはいったん帰りかけてまた引き返して来た。彼女はドリアンと別れ得ないのだ。しかしシビルに手紙を書いた。君は僕の愛を殺した、僕は快楽のためにのみ生きることに決めた。肖像画の口元が残酷の表情でゆがんでいるのを見たドリアンはわびの手紙を書いたが、その時訪れたヘンリー卿は、絶望したシビルが自殺したと知らせた。ドリアンは肖像画を2階の学生時代の勉強部屋に隠した。数年たって彼は画家ホールウォードに画を見せたあと、美しく成人したグラディスに画家が画のことを話すのを恐れ背後から刺し殺した。そして彼の言いなりになる化学者に画家の死体を処分させた。化学者はその後自殺し、ドリアンはグラディスと婚約した。シビルの兄ジェイムスは妹のあだがドリアン・グレイであることをつきとめ、彼の別荘の庭に忍びよったところを野ウサギと間違えられて射殺された。さすがに責任を感じた彼は、グラティスに婚約破棄の手紙を送り、肖像画の心臓にナイフを突きたてた。たちまちドリアンは倒れた。肖像画は美しい青年となり、その前の死体はドリアンと見分けのつかぬ醜悪な老人であった。
すべての芸術は、すなわち表層と象徴でなりたっている。
正直、映画版の「ドリアン・グレイの肖像」は、読書した時のようなゾクゾクした感覚はないのだが、肖像画の扱いが興味深い。恍惚と理想が投影されたドリアン・グレイを表現するために、ピンポイントでカラーが使用されているのである。また、ドリアン・グレイが落ちぶれていく中で絵も歪んでくるわけだが、絵の具が混ざったかのように絵画が歪んでいく。そして、あまりにも作風が変容しグロテスクな様となった絵画をこれまたカラーで提示するのである。理想を投影した絵画、理想と現実が乖離するものの、現実が絵画へ皮肉な形となって投影され、最終的に実体と虚像が一致する様の表象のアプローチとして本作の演出は興味深いものがあった。ただ、個人的に婚約者の演技が下手になる場面の狼狽シーンが好きだったたけに、その表現は薄味となっていたのは残念であった。