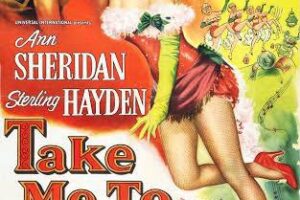今すぐ購入: 購買意欲はこうして操られる(2024)
Buy Now! The Shopping Conspiracy
監督:ニック・ステイシー
評価:60点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
SNSでちょくちょく話題となっているネットフリックドキュメンタリー『今すぐ購入: 購買意欲はこうして操られる』を観た。テーマ的に肩透かしな部分はあれども興味深い作品であった。
『今すぐ購入: 購買意欲はこうして操られる』概要
顧客に絶えず消費を続けさせるために、ブランド各社が行う販売戦略に鋭く切り込む社会派ドキュメンタリー。この策略が私たちの暮らしと世界にもたらしている真の影響とは?
Buy Buyin’ に Bye Bye
キリスト教は、宗教によって人々を導くべくメディアを用いた。単なる正論や教えでは人々はついてこない。故に物語を必要とした。そして、その物語を文字が読めぬ者や言葉がわからない者へ伝えていくために絵画やタンパンを使用した。ルーマニアにある世界遺産モルドヴァ地方の教会群ではスチェヴィツァ修道院を筆頭に、内壁/外壁をフレスコ画で埋め尽くしている。そこにはキリスト教の物語だけでなく、当時の脅威であったオスマントルコに対する恐怖も描かれており、人々に情報を伝え行動へと移す、または市民をひとつのベクトルへ向かわせる役割を担っていた。
時は現代、新聞、ラジオ、テレビにインターネットといった多様なメディアで氾濫している。その渦中であってもキリスト教と同じようにナラティブをメディアによって拡散し、人々の行動を制御するシステムは普遍的なモノとして機能している。アディダスは、アーティストの物語や背景と重ね合わせることで人々のアテンションを獲得、時にはカニエ・ウェストのような問題児を広告塔として起用し炎上商法で売り上げを伸ばしていった。また、Amazonのジェフ・ベゾスは、いつでも即時購入できる仕組み作りに尽力し、従来の買い物プロセスである「店に行く、商品を選ぶ、会計する」までの時間を短縮する方法として「1 Click購入ボタン」を開発した。そして執拗にA/Bテストを回し、消費者に考えさせる暇を与えず購入へと結びつけるシステムを確立させた。企業は広告やWebシステムを通じて購入へいたるナラティブや背景を構築していくわけだが、それは消費者に気づかれないように行われる。失敗すれば「QVC放送事故集」のように、消費者が抱く違和感により購買へと繋がらないからだ。
映画はこのような企業の理論を軸にグリーンウォッシュの問題へと眼差しを向ける。企業は環境に配慮しているように装いながらも、アフリカではプラスチックごみに汚染されており、二酸化炭素排出量も上昇している。見えない化、他国へ責任を委譲することによって地球規模で問題となっているのだ。
正直、その様をフィクションに落とし込んだ作品として『ウォーリー』が引用されているが、それを語るなら『くもりときどきミートボール』だし、日本基準で考えると有形商材だけでなく無形商材の観点からも過剰な購入の促しによる問題は深刻化しているように思える。特に日本の場合、「推し活」といった用語がマスコミや企業に都合よく握られてしまったがために、推しのために大量に同じグッズを買う、ボイスやメンバーシップ、スパチャなどに膨大な金と時間を費やす問題が発生している。また、日本ではオンラインカジノは違法であるが、ソシャゲの課金システムが似たような役割を果たしており、天井まで金を突っ込んでも狙いのキャラやアイテムが出ないといった事象はソシャゲをやったことがない人でも日常的に耳にする。しかも、イーロン・マスクがTwitterを私物化したあたりから、ナラティブを隠すといったことすらしなくなり、醜悪な物語が社会を支配するようになった。そのため、本作で語られる理論は片手落ち感は否めない。しかし、こういったドキュメンタリーが作られることに意義はある。