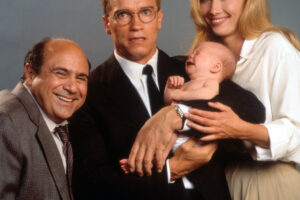描くべきか愛を交わすべきか(2005)
Peindre ou faire l’amour
監督:アルノー・ラリユー&ジャン=マリー・ラリユー
出演:サビーヌ・アゼマ、ダニエル・オートゥイユ、アミラ・カサール、セルジ・ロペスetc
評価:95点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
日仏学院で開催された「アラン・ギロディ&アルノー&ジャン=マリー・ラリユー特集 欲望の領域」にてラリユー兄弟の『描くべきか愛を交わすべきか』を観た。ラリユー兄弟は初であり、ポスターヴィジュアルからよくあるオシャレフランス映画だと思い期待していなかったのだが、冒頭から脳天を貫く圧倒的な掛け合いから始まる物語は異次元へと私を誘い心を攫っていった。
『描くべきか愛を交わすべきか』あらすじ
長年連れ添ってきた夫婦、ウィリアムとマドレーヌ。一人娘が家を出てから山の麓で2人静かに暮らしていた。絵を描くことが好きなマドレーヌは、ある日、繊細で教養のある盲目の男性アダムと恋人エヴァに出会う。やがて、アダムたちの家が火事で焼けてしまったことから2組のカップルは同居することになるのだが……。ジャン・ルノワールを思わせる大らかな官能性で欲望の衰えとそこへの回帰を描いた、光と闇の戯れが美しい作品。第58回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品。
絵の世界を提示しないこと
フランス田舎町にマドレーヌがやって来る。キャンバスを広げ、絵を描いていると、遠くの木から男が滑稽な動きでこちらへと向かってくる。思わず笑うマドレーヌ。男は立ち止まり、右を向く。そして、「誰かいるんだろ?男か?」と叫ぶ。彼は盲目であったのだ。盲目であると説明せずに、ショットのみで状況を説明するわけだが、ここでさらに興味深いことに気づかされる。彼女の絵をカメラは捉えないのだ。以降も、絵を描く設定が主張されるにもかかわらず、明確に彼女の描く絵は提示されない。どういった作風かは、家に飾っているフォーカスの当たっていない絵の断片でしか判断できないのだ。
この手法はモーリス・ピアラが『ヴァン・ゴッホ』で実践した手法に近い。絵描きを主軸に置く時、作品にフォーカスが当たりがちだが、映画はその背景を描いているはずである。なら、絵を描く者とその対象の関係性にカメラが置かれるべきであるといったロジックが『ヴァン・ゴッホ』にはある。
『描くべきか愛を交わすべきか』もそのロジックに従い、絵を描く行為によって生まれる距離感から人間心理の掬いあげている。ここで、盲目の男の設定が活用されており、彼が登場するだけならば物語として障がいが消費されているに過ぎないが、彼の視点を強制的に観客へ付与させることで解消されている。ウィリアムとマドレーヌが闇を辿って家路へと向かう場面では、数分間に渡る闇が画を覆いつくすのである。事件性のある悲鳴と静寂が観客の五感を刺激し、映画へと向かわせる役割を担っており、それは絵を魅せない点と共鳴することとなるのだ。
それにしても、盲目の男が「さあ、案内するよ。絵の世界へ!」といって右を向くと廃屋が見えている最初の場面が黒沢清映画さながらの怖さを持っていて戦慄した。